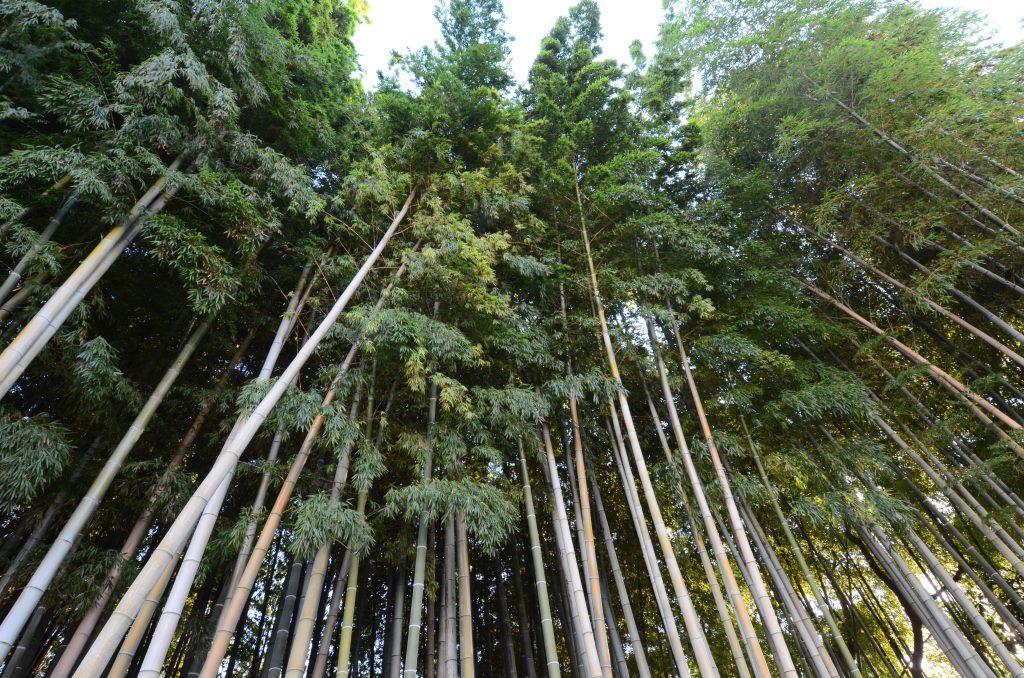1月17日、国府台天満宮境内で「辻切り」が行われました。
ちいき新聞の1月29日号記事「市川民話のつどい」にも登場した「辻切り」は、この地区で室町時代から行われている行事です。

公開 2021/02/22(最終更新 2022/03/09)

ショー
市川・船橋担当。主に市内の歴史、民話、建造物、イベント等の情報発信。個人的には1980年代より、東京・昭和初期の面影を撮影中。1989年銀座ニコンサロンで個展「都市観察―木造3階建てのまわりでは」、2010年オリンパスギャラリーで「トーキョー・人模様」
記事一覧へ民話にも登場する国府台地区の継承行事
「辻切り」は、危害を加える悪霊や悪疫が地区に入るのを防ぐため、地区の出入り口となる四隅の辻に、わらで編んだ3m近い大蛇を置いて退散させることから起こった名称です。
市川市内で当時の風習の姿を伝えており、市の指定無形民俗文化財となっています。

当日、会場で行事に参加していた「辻切り保存会」の小宮さんに話を聞きました。
「先祖代々からの言い伝えを守り、毎年1月17日に天満宮さんで行っています。元々は宮廷行事のまね事から始まったと聞いています。昨年からのコロナ禍で大変な年になっているので、今回は特に気持ちが入ります」
保存会に地区消防団も加わり大蛇を編む
当日会場では見物人が作業場所に近づき過ぎないようロープが張られ、マスク着用など感染防止対策への協力を呼び掛けて行われました。

午前9時前から保存会のメンバーが社殿前で大蛇の頭部、胴体を編み始めます。
目玉は、2年前の大蛇のわらを焼いた灰を紙に包み、黒目を書き入れたもの。
耳はビワの葉。
境内の一番大きいケヤキの枝にロープを渡し、2m近い尾の部分を編み込みます。
消防団の若手も作業に加わりました。
各パーツができたら社殿前で組み上げ、大蛇の首に塞座三柱大神(さえのくらみはしらおおかみ)のお札を掛けます。
この間に、小宮さんが見物人たちに辻切りの歴史を解説しました。

完成した4体の大蛇は口を開け、お神酒を飲ませた後、それぞれ国府台地区の四隅にある木にくくり付けられました。
大蛇たちは今この瞬間も、鋭くにらみを利かしています。