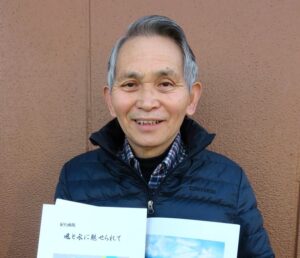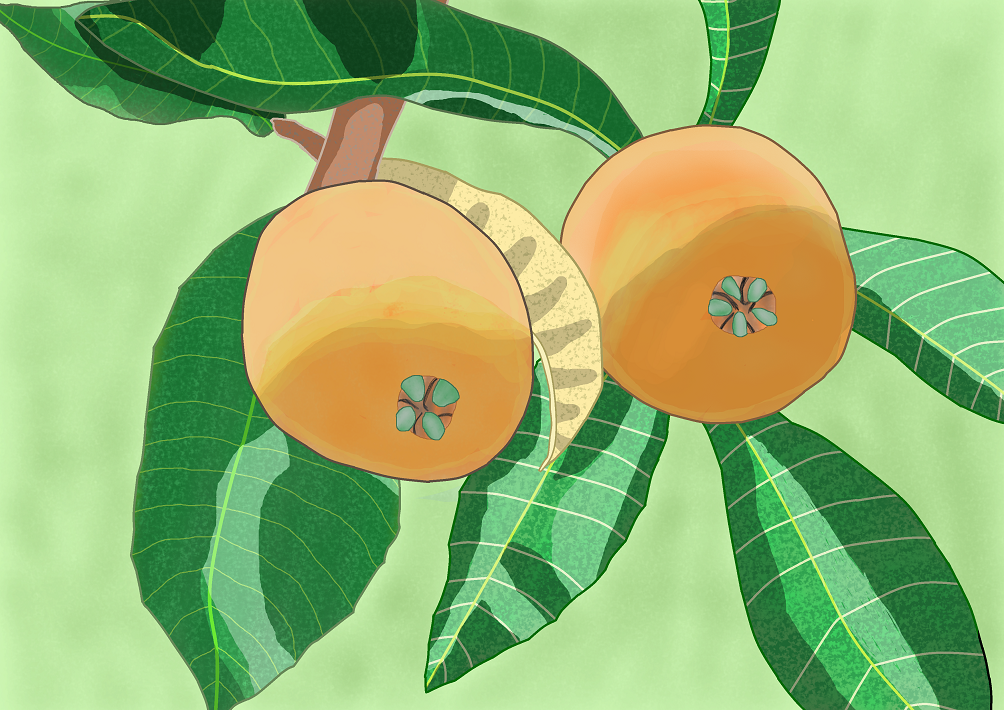近代日本では鉄道の開業によって地域が開発されましたが、四街道市を舞台に、鉄道と地域の発展を地道に研究しているグループがあります。
研究成果は毎年、定期的に発表されています。

公開 2021/12/26(最終更新 2023/02/03)

ソバ
大手新聞社の記者を続け、定年延長も終わったので、地域の話題を取材したいと、地域新聞様にお世話になっています。明るく、楽しく、為になる話題を少しでも分りやすく紹介したいとネタ探しの日々です。子どもの頃から麺類が好きなのでペンネームにしました。
記事一覧へ子規も鉄道で旅行 旅行四街道駅前に句碑
四街道地域の鉄道の歴史は古く、1894(明治27)年7月に総武鉄道市川〜佐倉間が開業。
同年12月には東京・本所〜佐倉間が開通し、四街道駅も開設されました。
約25人の会員で活動する「鉄道を通して四街道の歴史を学ぶ会」は、こうした歴史を振り返り、2014年に開業120周年の展示会を四街道市在住の楠岡巌さんらが中心になって開催。
その後も鉄道にまつわる展示会や、鉄道関連の見学会を開いており、展示会では、俳人、歌人として有名な正岡子規(1867〜1902)を鉄道に関連して取り上げたことも。
子規は佐倉まで鉄道で旅し、紀行文「総武鉄道」に作った20句が掲載されています。
「棒杭や四ツ街道の冬木立」は、子規が四街道駅で詠んだ一句。

正岡子規の石碑
これは、開業間もなく、冬の情景を描写したもの。
現在のJR四街道駅北口の広場に、この句を刻んだ句碑があります。
同会は、こうした鉄道にまつわる郷土史を調べています。
戦時中の軽便鉄道 写真撮影地も紹介
展示会では明治時代以降の鉄道を中心にした地図、四街道の開拓の歴史、戦時中に稼働した線路の幅が狭く、車両も小型だった軽便鉄道、昭和30年代の切符、鉄道写真撮影地などを紹介しています。
撮影地として有名なのは略称「モノサク」。
JR総武線物井〜佐倉間で、線路にフェンスやガードレールがない区間があります。線路沿いにあぜ道があり、田園風景が広がるので、列車の絶好の撮影スポットとなっているのです。
会員も撮影し、作品を展示しています。
展示会は新型コロナウイルス感染症の流行で2020年は中止しましたが、21年は7月と12月に無事に開催。

会代表の工藤博孝さんは「かつての鉄道は窓を開ければ外の空気が入り、発車間際に慌てて乗り込むことも比較的自由にできました。のんびりした乗り物で楽しかった」と目を細めます。
一緒に活動したいメンバーは、いつでも歓迎とのこと。
※問い合わせ
電話/090-4388-3643 工藤