大切な遺言が手続きの不備や紛失で実行されなかったら…?
そんな事態を防ぐために利用できる制度があります。
預かってもらえば何かと安心。
「自筆証書遺言書の保管制度」についてまとめました。
取材協力/千葉地方法務局船橋支局
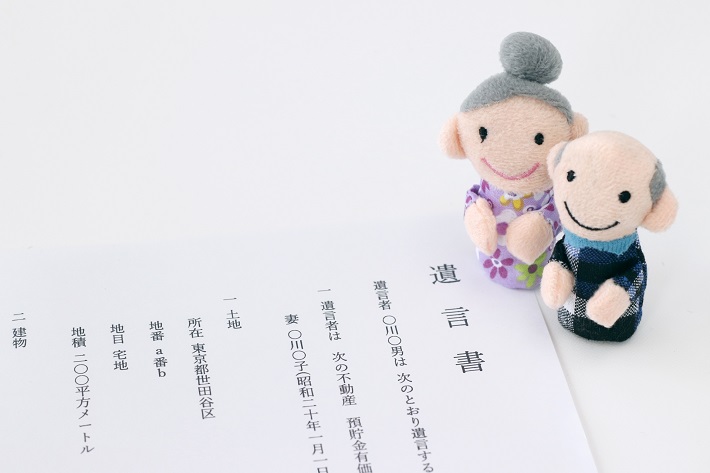
公開 2022/02/25(最終更新 2022/02/16)

編集部 R
「ちいき新聞」編集部所属の編集。人生の大部分は千葉県在住(時々関西)。おとなしく穏やかに見られがちだが、プロ野球シーズンは黄色、Bリーグ開催中は赤に身を包み、一年中何かしらと戦い続けている。
記事一覧へ目次
自筆証書遺言書の保管制度とは?
遺言には自分で書く自筆証書遺言、公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。
自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて手間や費用はかかりませんが、自宅や貸金庫などで保管されることが多いため、
・紛失
・相続人による改ざん
・遺言書の存在が気付かれない
…といった心配がありました。
また、遺言書を開封するには家庭裁判所を通して「検認」という手続きが必要で、勝手に開封すると5万円以下の過料が課されます。
これら自筆証書遺言にありがちなトラブルを減らすため、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。

「遺言書 ほかんガルー」
「自筆証書遺言書保管制度」により、法務局で自筆の遺言を預かってもらうことが可能になりました。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
・公的な機関で保管してもらうことで、自分保管で生じがちなトラブルが回避できる
・面倒だった検認手続きが不要に
作成した遺言書を預けるには
・保管先を決め、保管を申請する日時を予約
・申請に必要な書類をそろえる(法務省HPでダウンロードできます)
・申請に必要な手数料3,900円を用意
保管所へは必ず遺言者本人が足を運ばなくてはなりません。
また、保管所で遺言内容の相談はできないので、注意しましょう。
遺言書の保管を申請するには?
1.自筆証書遺言に係る遺言書を作成
※不備があると無効になることもあるので要注意!
2.保管の申請をする遺言書保管所を決める
保管の申請ができる遺言書保管所
◇ 遺言者の住所地
◇ 遺言者の本籍地
◇ 遺言者が所有する不動産の所在地
これらいずれかを管轄する遺言書保管所から選びます。
ただし、すでに他の遺言書をいずれかの遺言書保管所に預けている場合は、その遺言書保管所になります。
3.申請書を作成
申請書は、法務省HPからダウンロードするか、法務局(遺言書保管所)窓口に備え付けの用紙を使用します。
4.保管の申請を予約
5.保管の申請
次の(ア)から(オ)までの物を持参して、予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所へ
(ア)遺言書
ホッチキス止めはしないこと。封筒は不要
(イ)申請書
あらかじめ記入しておく
(ウ)添付書類
本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3カ月以内)
※遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
(エ)本人確認書類(有効期限内のものをいずれか1点)
●マイナンバーカード ●運転免許証 ●運転経歴証明書 ●旅券 ●乗員手帳 ●在留カード ●特別永住者証明書 等、顔写真入りのもの
(オ)手数料
1通につき3,900円(必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼る)
※一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されません
6.保管証を受け取る
手続終了後、遺言者の氏名・出生の年月日・遺言書保管所の名称および保管番号が記載された保管証が渡されます。
遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求等をするときに保管番号があると便利なので、大切に保管しておきましょう。
遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けていることを家族に伝える場合にも保管証を利用すると便利です!
詳しくは法務省ホームページの「自筆証書遺言書保管制度」のページから。
申請日時の予約や申請書のダウンロードもできます。


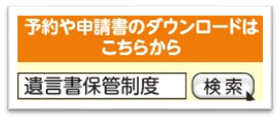
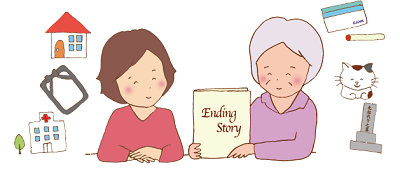








0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)









