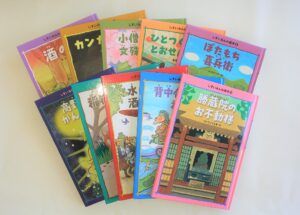酒々井町で長年、農具や刃物を造ってきた鍛冶工・稲坂徳太郎さんは昨年、厚生労働省の「卓越した技能者(現代の名工)」に選ばれました。
今年1月には89歳になりましたが、「体を動かすことが健康の秘訣」と元気いっぱいです。

公開 2022/03/09(最終更新 2023/02/03)

ソバ
大手新聞社の記者を続け、定年延長も終わったので、地域の話題を取材したいと、地域新聞様にお世話になっています。明るく、楽しく、為になる話題を少しでも分りやすく紹介したいとネタ探しの日々です。子どもの頃から麺類が好きなのでペンネームにしました。
記事一覧へ13歳で弟子入り 厳しい鍛錬を積んで
実家は代々続いた鍛冶工で、稲坂さんは18代目となります。
13歳で祖父と父に弟子入りし、厳しい指導を受け、鍛錬を重ねたといいます。
「祖父からは、鉄の棒を金づちで真っすぐにたたいて四角にする技術を学んだ」と懐かしそうに振り返ります。
稲坂さんの造る、鍬、鋤などの農具や包丁は、「佐倉鍛造刃物」として知られています。

1本の鉄から金づちと炎だけで造りだす「総火造りの手法」を受け継いでおり、鉄を火で熱してたたき、最後は砥石で研いで仕上げていきます。
「仕事を始めたら、休みなしで続ける」というほどの集中力で取り組みます。
鍬は1日、鎌や包丁は半日で完成できるとはいうものの、その作業はスムーズに進むわけではない。全てを型にはめて造るのではなく、たたいて形を整えながら丁寧に作業を進めていきます。
それでも、「私が思った通りのものは100%できない」と稲坂さんは話します。
使うほどになじむお手植えの鍬も製造
そうやって出来上がった製品は、使用年月の経過や使い手の愛着とともに成熟していきます。
「切れ味が良く、使いやすいものを造っています。使っているうちに手になじみ、より使いやすくなります」と稲坂さんは続けます。
鍛冶工の輝かしい実績としては、2003(平成15)年5月に木更津市内で実施された「第54回全国植樹祭」での、(当時の)天皇・皇后両陛下のお手植えの際の鍬を製造したことが挙げられます。
その時の写真は自宅玄関の壁に飾ってあり、稲坂さんは訪問客に懐かしそうに説明します。

「百歳まで続ける」仕事が健康の秘訣
農具の注文は昭和30年代まで多かったですが、その後は耕運機などの導入や、手作りではない安価な農具が増えて、次第に減ったといいます。
しかし、「注文がある限り仕事は続ける。100歳まではやるつもりだ」と、意欲を熱く語ります。
鍛造の他、米作りなどの農業にも従事。
今後は長男の義徳さんが19代目、義徳さんの息子さんが20代目を継承予定です。
「体を動かすことが健康の秘訣」と、稲坂さんはその年齢を感じさせないほどに、豪快に笑いました。
※問い合わせ
電話/043-496-1601 稲坂