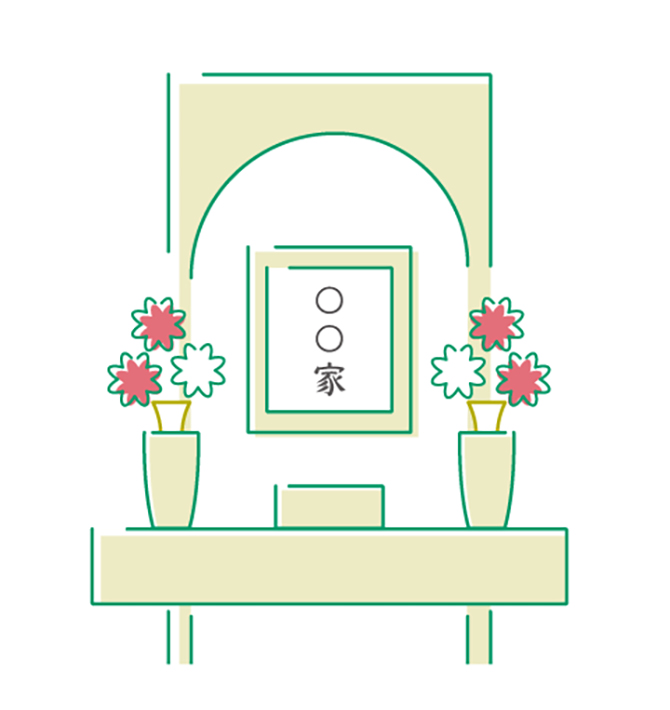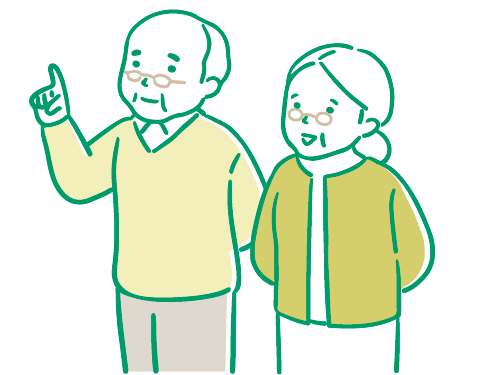生前墓とは、生きているうちに自分が入るお墓を自分自身で建てることをいいます。
その種類や費用、選び方について伺いました。

馬場 政彦さん
公開 2022/06/24(最終更新 2022/06/23)

縁起が良い「寿陵」 相続税対策にも
終活の一環で、生前墓を検討する人は年々増えています。大体50代から、自分の両親のお墓のことと一緒に意識しだすケースが多いようです。生前墓は「寿陵(じゅりょう)」ともいい、日本や中国では長寿・子孫繁栄につながる縁起が良いこととされてきました。ただ、それだけで生前墓を建てる人は多くはありません。「子どもに迷惑をかけないように、自分のお金で建てておきたい」と選択する人がほとんどです。
墓地、墓石、仏壇、仏具などを祭祀(さいし)財産といい、これらは非課税になります。お墓のためにお金を残しておいても相続税はかかりますし、ローンを組んでも残債は課税対象になります。つまり、生前にお墓を購入しておいた場合のみ節税になるわけです。
納骨は四十九日までにするのが一般的ですが、亡くなった後にお墓を購入すると間に合わない場合も。慌てて希望とは違う場所に建ててしまうこともあります。また近年、横長でモダンな洋型墓石の人気が高まり、さまざまなデザインが選べるようになりました。どんなデザインにしたいかも、生前だからこそ考えられることです。
霊園・墓選びの優先順位
1.予算
2.立地
3.環境
4.広さ
霊園見学時のポイント
安さだけで選ばずに、気持ちよくお墓参りができる環境か、管理が行き届いているか確認を。
通路などの共用地の清掃状況、木の剪定状況などもチェックしましょう。
近年需要が高まる永代供養墓
お墓の種類は、先祖代々受け継がれる一般墓と、霊園や墓地の管理者が遺族に代わって供養・管理をしてくれる永代供養墓に分かれます。これまでは家族ごとに建てた一般墓に入るのが主流でしたが、お墓を継ぐ親族がいない、遠方に住む子どもに負担をかけたくないなどの理由から、継承者が不要な永代供養墓を選ぶ人も増えてきました。
永代供養墓は、他の人の遺骨と合同で埋葬される合祀(ごうし)という形式を取るもののことを指しますが、最初から合祀される合祀墓と、個別に埋葬した後に一定期間を過ぎてから合祀される永代供養付き個別墓があります。
墓石代や年間管理費がかからないところが多いので、比較的コストを抑えられるというメリットも。ただし、合祀した後は遺骨を回収できません。また、個別にお参りができなくなるので、家族とよく話し合って決めましょう。
檀家離れが進み、永代供養墓に変えたいという人もいますが、墓じまいにも費用がかかるので、総額をしっかり比較して検討を。
継ぐ人が必要
一般墓
継ぐ人が不要
・永代供養墓(合祀墓)
・永代供養付き個別墓
永代供養墓にはどんな選択肢がある?
一口に永代供養墓と言っても、その形状やかかる費用はさまざまです。
樹木墓地(樹木葬)

墓石の代わりに樹木をシンボルとするお墓で、シンボルツリーの周りに遺骨が埋葬されます。
区画の面積などにより、相場は1霊位30~50万円前後。
年間管理費不要の場合が多く、予算を抑えたい人に人気です。
最近はペットと一緒に入れる所も。
納骨堂
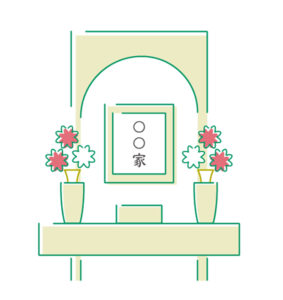
個人、夫婦といった単位で遺骨を収蔵することができます。
立地や納骨堂のタイプ、収骨する人数によって費用が異なり、相場は10~150万円と幅があります。
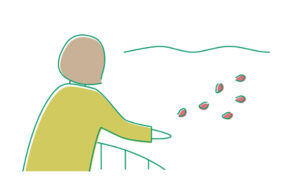
この他、「海洋葬」をはじめとする散骨という方法もありますが、家族としては手を合わせる対象が欲しいもの。
事前に家族の理解が必要です。
費用や子どもの負担を軽減でき、かつ自分の価値観に合致するお墓をじっくり選択しましょう。