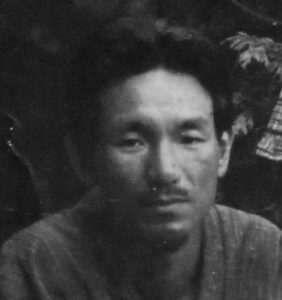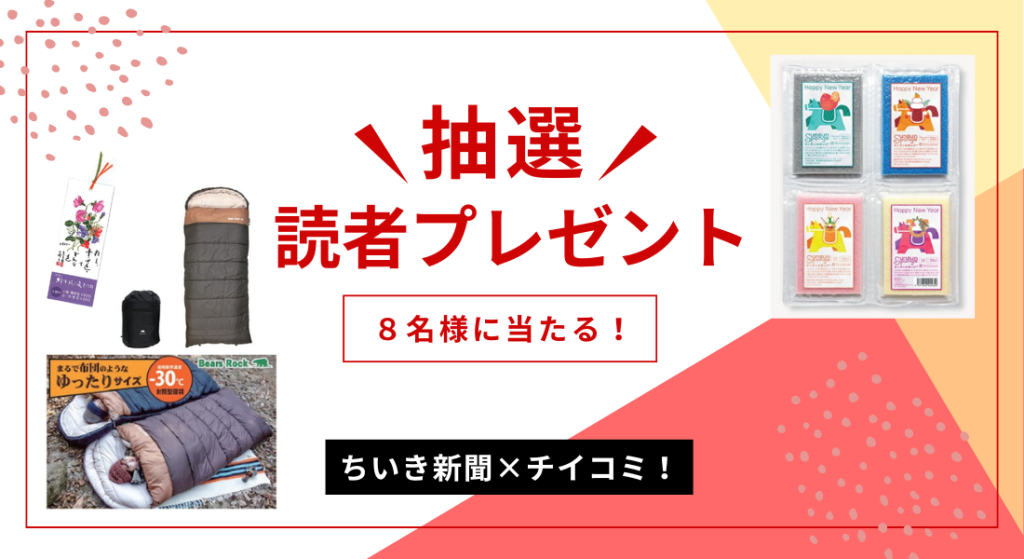特定外来生物として指定されている水生植物が、手賀沼にたくさん繁殖していることをご存じでしょうか。水質・生態系などへの影響や農業・漁業被害などが懸念されているナガエツルノゲイトウとオオバナミズキンバイについて、千葉県では専用船や手作業による駆除作業を行なっています。駆除の概要について千葉県水質保全課を取材し、現場で手作業に従事するライターが現地ルポをお届けします!
取材・撮影協力 雉間英樹さん
公開 2022/07/06(最終更新 2022/07/22)

野中真規子
人・土地・物語をつなぐ 文化プロデューサー/編集者 イベントやメディアなどのプロデュース、ディレクション、制作を行い、これまで1,500人以上の「豊かで楽しく生きる人」に取材。自己探究の過程で見えてきた、暮らしや意識が変わる瞬間について発信中。https://www.instagram.com/teganumakki/
記事一覧へ目次
水面にマットのように群生、環境への影響も懸念される
駆除の対象となっている水生植物は、ナガエツルノゲイトウとオオバナミズキンバイの2種です。いずれも地上や水上で枝分かれしながら茎を伸ばし、茎は絡まり合いながら、水上でマット状の群落を形成。そこから波や増水、風などによって一部が漂流すると、別の場所に新たに定着します。手賀沼の水面に、まるで小さな島のように浮かんでいる様子を見て気になっていた方もいるのではないでしょうか。
ナガエツルノゲイトウは南米原産の植物。茎に節があり、茎がちぎれても、節から根を出し、繁殖します。

オオバナミズキンバイは中南米原産で、生育条件によっては茎の断片や1枚の葉からも根を出し、繁殖します。

現在この2種が手賀沼やその流域河川で急速に繁殖。植生帯の周囲まで入り込み繁殖する、船等の通行を阻害する、施設の取水口をふさぐ、農地へ侵入する、などの恐れがあり、水質・生態系への影響や農業・漁業被害などが懸念されています。
平成28年から市民団体等により局地的な駆除が実施されていましたが、手賀沼全体の問題解決には至らないため、令和2年度から千葉県による大規模駆除が始まりました。
専用の刈取船と手作業による駆除を実施中
千葉県による駆除が始まったきっかけは、令和元年の調査により、10万平方メートルにわたって外来水生植物が繁茂していることが判明したことだそうです。
千葉県水質保全課の担当者・谷翠さんによれば「国から特定外来生物の防除に係る確認を受け、手賀沼の特性を踏まえた駆除方法を検討し、令和2年度から水草刈取船を使用した外来水生植物の駆除を開始。令和3年度までに、手賀沼の西側の群落約2万7千平方メートルの刈取りを行い、手賀沼とその流域河川における繁茂面積の約4分の1の駆除が終わりました。また令和3年度には、前年度に駆除した場所に漂着・再繁茂していた外来水生植物も刈り取りました。令和4年度は手賀沼南西部・大津川河口部と過年度駆除対象区域に漂着・再繁茂した1万8千平方メートルを駆除する計画のもと、現在作業が進められています」とのこと。
使用している水草刈取船は以下の3種です。
ハーベスター(セイレイ興産株式会社)

ベルトコンベア上に刈取ったマット状の植物を載せながら回収します。水草を刈取り、駆除物を積込んでの運搬も可能です。
コンバー(宇部工業株式会社)

水底に伸びた水草の根の部分を水底の泥ごと掘り起こし、水面付近で泥を洗い落とした後で、水中から取り上げます。陸水両用です。
ハイドロモグ(株式会社テクアノーツ)

水草の根を陸域から切り離して掴み上げ、運搬船に積込み、陸まで運搬します。
各刈取船は、いずれも操作にたけたベテランのオペレーターさんが担当しています。
ハーベスターのオペレーター歴25年、山本博行さんによると、水深がまばらで底が見えない手賀沼では、感覚を頼りに最適な船の位置や刃の動きを細かく調節しながら作業する必要があり、マット状に固まった植物を根こそぎ刈り取り、なおかつ収集するまでの過程で周囲にちぎれた茎や葉が散らかさないよう神経を使うそうです。
刈取船に加えて、ヨシなど岸に生える植物の根本に入り込むように生えたものや、ちぎれて水面に浮かんだ細かい茎などは手作業にて刈り取り・収集を行っています。
細かく根気のいる作業、手による駆除を体験
今年はライターも手作業での駆除メンバーの1人として刈取に従事しています。ウエーダーを着てボートで岸辺まで行き、沼に立ち込んで作業します。
手作業では、専用船の届かない狭い場所や、植物の合間に生えているものを抜き取ったり、ちぎれて水面に浮かんでいる茎をつまんで集めたりしていきます。沼底がやわらかい場所やすべりやすい場所では、足元を取られそうになるので、ヨシにしがみついたりしながら作業するのがなかなか大変です。

ナガエツルノゲイトウもオオバナミズキンバイも、根がとても長く伸びているのですが、根こそぎ取り除かなければ新たに繁茂してしまいます。ナガエツルノゲイトウは茎が中空になっていて切れやすいので、根本に近い部分を掴み、ゆっくりと抜き取ります。周囲に別の植物がなければまだやりやすいのですが、ヨシなどの根本に混じって生えていることも多く、その場合は根っこ同士がからみ合っているので、とても抜き取りにくい!指を根本につっこんで探りながら慎重に抜き取ります。
駆除11年目のベテラン、吉田周市さんは、根っこを掘る作業を繰り返して指の関節がこんなに太くなりました。繊細さと力強さがいる作業なのです。

ナガエツルノゲイトウの根っこはこんなに長く張っています。複雑な形のものは、さらに抜くのが大変です!

ちぎれた数センチ程度の茎や葉からでも再繁茂することがあるので、目を皿のようにして水面を見つめ、収集します。

オオバナミズキンバイの根っこは複雑にからみあっているので、これまた取りにくいです。

こうして集めた水生植物はかごに入れて、船に積み込み、桟橋まで運びます。各刈取船で取ったものも桟橋に集められ、乾燥後に焼却されます。

地域住民・団体のみなさんと連携しながら防除・監視を
駆除の計画は毎年度見直されており、流出拡大、生態系への影響等のリスクに応じて、優先度の高い群落から順次、計画的駆除を実施していく予定だそうです。

「水草刈取船による駆除後にも、他所からの群落の漂着や再繁茂が見られています。このため、駆除済みの箇所を監視しながら、人力による作業が可能な群落に駆除を実施し、再繁茂するナガエツルノゲイトウとオオバナミズキンバイを早期に除去して、群落の新たな成長を防ぐことが必要です。今後も地域住民・団体等のみなさんと連携協働して防除・監視体制を構築していきたいと考えています」(谷さん)。
地域の憩いの場である手賀沼を、みんなで守っていこう
水生植物を駆除作業に関わるうちに感じたのは、大量に駆除した植物が何かに利用できればよいということ。現在のところ実用化には至っていないようですが、堆肥化の実証実験も行われているとのことで、今後さらに研究が進んで、何らかの活用法が見出されるとよいと思いました。
ちなみに駆除作業中は、沼に捨てられた家庭ごみやルアー、釣り糸などの釣りごみも非常に多く目にしました。部分的には市民団体などがクリーン活動をしていますが、まだまだ汚れているところはたくさんあります。
地域の大切な資産である手賀沼。大正時代には周囲の景観をもとめて文人が別荘を立て、昭和20年代ころまでは沼の底や泳ぐ魚が見えるほど水が澄み、子どもたちが泳ぎ、おいしいうなぎが獲れたといいます。
今回駆除されているナガエツルノゲイトウとオオバナミズキンバイのような外来水生植物が国内に繁茂しているのは、もともと人が家庭用の水槽にあったものを持ち込んだためという説もあります。現在特定外来生物に指定されているその他の外来植物や外来動物も、そもそも人間の行動が原因で繁茂・繁殖していることは言うまでもありません。あらためて、むやみに家庭のものを自然に放たないようにしながら、環境を守っていきたいですね。
なおナガエツルノゲイトウとオオバナミズキンバイは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で特定外来生物に指定されています。飼育・栽培・保管・運搬・販売・輸入などが禁止されているので、持ち帰ったりしないようにしましょう。地域住民やボランティア団体等などによる小規模な活動の場合も、これらの植物の運搬と保管には一定の要件を満たすことが必要です。
千葉県水質保全課では、Twitterの「千葉県水草バスターズ」でも外来水生植物の情報や、住民等が行う環境保全活動に関する情報を発信しているので、ぜひチェックしてみてください。
「千葉県水草バスターズ」
https://twitter.com/capbusters
千葉県水質保全課
HP/https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/
住所/千葉県千葉市中央区市場町1番1号本庁舎3階
休業日/土日祝・年末年始
問い合わせ/043-223-3821