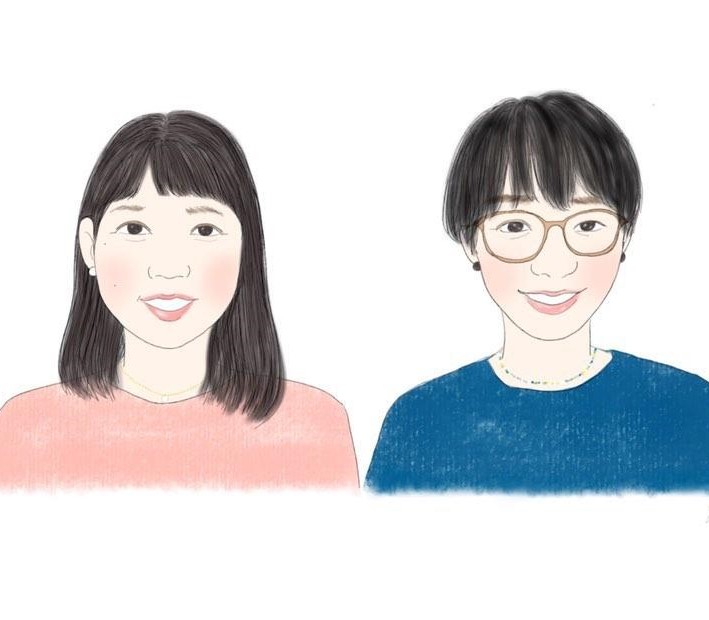御成街道沿い長沼交番の隣、駒形観音堂の境内に鎮座する大仏。
なぜここに大仏が?
長沼郷土歴史クラブの三角さんと五藤さんを取材しました。

公開 2022/12/05(最終更新 2022/12/02)

実は鎌ケ谷大仏より大きい駒形大仏
長沼の駒形大仏は、腹前で定印(※両手の人差し指と親指を付けて輪を作った手の形)を結ぶ如来坐像。
1703(元禄16)年鋳造の銅製で高さ2.36m。
1974年には千葉市指定有形文化財に指定されています。
長沼郷土歴史クラブを訪ねると、徳川家と縁の深い長沼の歴史について教えてくれました。

鷹狩りを好んだ家康は、船橋から八鶴湖の東金御殿までを結ぶ御成街道を作らせたことで知られています。
3代将軍家光が東金へ向かう際に愛馬が傷つき、その屍を村人が供養したのが奥之院の始まり(※千葉北高校隣に現存)。

愛馬が家光の身代わりになったと言い伝えられ、「身代わり観音」として、今なお近隣の信仰を集めています。
今からおよそ320年前、奥之院の近くに約60の村から浄財寄進を受けて建立されたのが「駒形大仏」です。
1739(元文4)年には、さらに多くの人々が集う、現在の駒形観音堂の境内へ移されました。
大仏の背面に、寄進した念仏講中や村民の名前がびっしりと刻まれていることから、全ての者が心安らかに暮らせるようにと願う当時の信仰の深さが感じられます。
江戸時代から人馬の安全と疫病退散を願ってきた慈悲深い優しい顔立ちの駒形大仏。
「あまり知られていませんが、実は、鎌ケ谷大仏よりも大きい大仏様です。ぜひ多くの方に見に来てほしい」と同クラブの五藤さん。
毎年2月18日の例祭にはご開帳があり、観音堂の馬頭観音像の姿が見られるそうです。
かつて長沼はその名の通り沼だった
江戸時代に新田開発が行われた「長沼」。
この地名は、村の西方にある御瀧神社の滝を水源とした長く伸びた長沼池と呼ばれた沼があったことに由来。

「子どもの時に沼に入り、フナを手づかみして遊んだものです」と、今はグラウンドとなった場所を眺め、懐かしそうに話す同クラブ会長の三角さん。
奥之院から御成街道に向かう道の途中にある御瀧神社は、沼の水源となった小さな滝のあった場所。
家康が喉を潤したとも伝えられ、地元住民に「水神様」「権現様」と呼ばれ今でも大切にされています。
生活に根差した信仰心で集落をまとめた「長沼」。
道端に、由来のある石仏や石塔が今もひっそりとたたずんでいます。
(取材・執筆/ミモザ)
HP/https://nnn360.jimdofree.com/