子どもの「お口ポカン」は黄信号!?
小学生の虫歯が減少する一方、口が開いている、口呼吸をしているなど口腔(こうくう)機能の発達が不十分な児童の割合が増加傾向にあります。
症例と影響について調べました。
取材協力/千葉県歯科医師会

公開 2023/03/06(最終更新 2023/03/06)

口周りの発育不全、保険診療も可能に
口腔機能発達不全症とは、15歳未満の健康な子どもにおいて、食べる・話す・呼吸するなどの機能や発達に問題がある状態を指します。
学齢児童の8割近くが当てはまるとの報告があり、今後も増えていくと予測されています。
これを受け、2018年には、口腔機能発達不全症の検査や治療について健康保険が適用されるようになりました(2022年には対象年齢が18歳未満に拡大)。
子どもの口元に注目して早期発見を主な症例には以下のようなものがあります。

生えるのが遅い歯がある(平均的な歯の生える時期より乳歯が6カ月、永久歯が1年たっても生えない)・食べ物を飲み込むのが苦手・かむ時間が短いか長過ぎる・偏食や小食で体重が増えない・いつも口が開いている・指しゃぶりや爪かみがやめられない・正しく発音できない音がある(カ・サ・タ・ナ・ラ行)・いびきがひどい…など。
子ども自身は自覚していないことが多いので、保護者が早く気づいて歯科医師による指導や管理、治療につなげることが重要です。
生涯にわたり重要な健康な口の土台作り
舌を中心とする口周りの筋肉、すなわち口腔機能の発達は、食べる・呼吸するといった生命に極めて重要な働きを担うため、歯並びや顔立ちだけでなく全身に影響を及ぼし、学習能力や運動能力にも支障が生じるとされています。
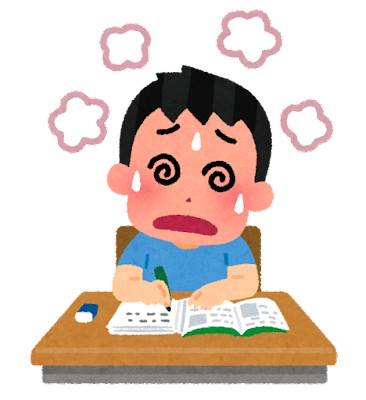
また、成人期のいびきや睡眠時無呼吸症候群の発症要因となったり、高齢期には摂食・嚥下障害から要介護となる可能性も指摘されています。
感染症対策のマスク着用で口呼吸になりやすく、友達との会話も抑制されるなど、子どもの口腔機能の健やかな発達が懸念される昨今、かかりつけ歯科医院で定期的にチェックしてもらうことが大切です。
















