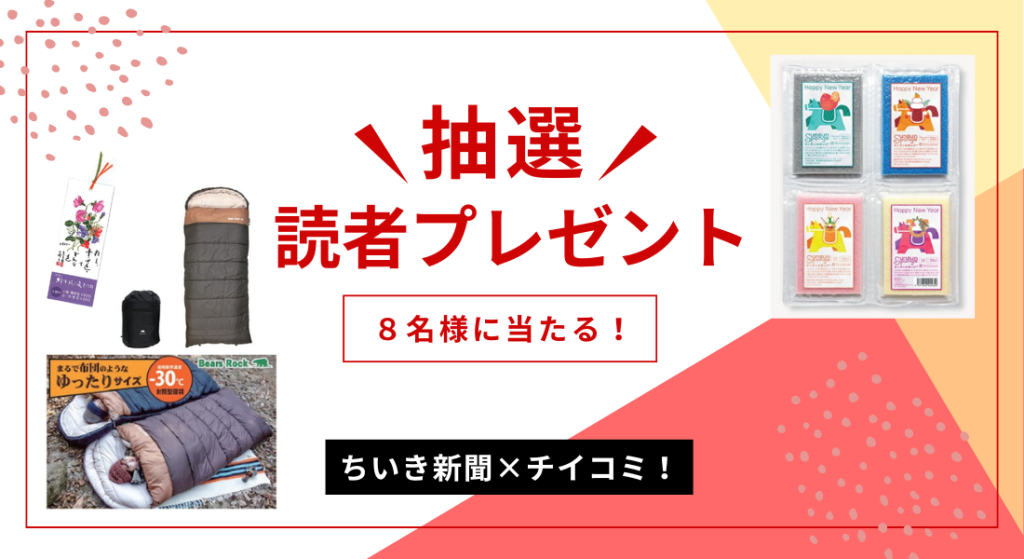私たちの暮らしに欠かせない、ガソリンなどの石油製品。
京葉臨海工業地帯からこれらの物資を輸送するのに活躍しているのが、千葉県では唯一の貨物専用の地方鉄道・京葉臨海鉄道(通称:りんてつ)です。
\動画でも紹介中!/

りんてつの役割や会社の歴史を同社取締役で運輸部長の石井一男さんと総務部長の秋葉政範さんに教えてもらいました。

石井さん(右)と秋葉さん
こちらの記事もおすすめ
公開 2023/05/31(最終更新 2023/05/30)

編集部 モティ
編集/ライター。千葉市生まれ、千葉市在住。甘い物とパンと漫画が大好き。土偶を愛でてます。私生活では5歳違いの姉妹育児に奮闘中。★Twitter★ https://twitter.com/NHeRl8rwLT1PRLB
記事一覧へ目次
国内で最も歴史のある臨海鉄道
京葉臨海鉄道は、JRの蘇我駅から袖ケ浦市の京葉久保田駅を結ぶ貨物専用の鉄道。今年で創立61年と、国内にある9つの臨海鉄道の中で最も歴史が古い路線です。
主に輸送するのは、京葉臨海工業地帯で製造されたガソリンや石油、灯油、重油などの石油製品。
千葉市~市原市・袖ケ浦市にまたがる京葉臨海工業地帯の石油精製会社近くに9つの駅を構え、各駅から運ばれた貨物を千葉貨物駅で連結し、蘇我駅へ。そこからJR貨物にバトンタッチし全国に運ばれます。
蘇我駅へ運搬する貨物(発送)の約8割が石油製品で、その他にも化石燃料から作られる樹脂をはじめとする工業物資、飲料水や耐火レンガといった生活物資もコンテナを用いて運んでいます。
逆に全国から届く貨物(到着)は半数をコンテナが占めており、その中身は生野菜や砂糖、米などの食料品も含まれているそう。
2022年度までの累積輸送量は1億1892万トンにも上ります。
一度にたくさん運べる貨物列車
貨物列車での輸送のメリットは「大量輸送」「環境性」「時間正確性」の3点。
1両のディーゼル機関車でどのくらいのタンクをけん引できるかというとマックスで22台。タンク車は自重が18トンでガソリン等の積載量が42トンで合計60トン。一度に最大1,320トンもの量を運べる計算です!

さらに、トラックなどと比べてCO2の排出が少ないため環境にも優しく、渋滞などの影響を受けず荒天時を除けば時間通りの運搬が可能です。
一方でトラックは機動性に優れているため、輸送量や距離によって使い分けをしているということでした。
古くから物流手段として利用されてきた貨物列車ですが、カーボンニュートラルやSDGsの観点からみると次時代に即した物流といえるのかもしれません。
物流を支える千葉貨物駅
普段は一般の人は入ることができない同社の中核拠点「千葉貨物駅」を特別に見学させてもらいました。

1997(平成9)年に名称を村田駅から千葉貨物駅に変更。現在は倉庫も保有し、輸送だけでなく保管や集配の拠点としても機能しています。
運行を管理する「CTCセンター」も敷地内にあり、まさにりんてつの要といえる場所。
同社が所有するディーゼル機関車は7両(うち1両が電気式ディーゼル機関車)あり、そのうち5両を常時稼働させ、計画的に物資を輸送しています。
車体はりんてつのイメージカラー「マリンブルー」。
最も古い機関車はこちら、昭和42年製の「KD55103」です。

実は「KD55103」はマニアの間では「名機」として有名な一台。同社の運転士も「操作性が全く違う」と口をそろえて絶賛するほどです。
最新の機関車は、2021(令和3)年に導入された電気式ディーゼル機関車の「DD200」:愛称「RED MARINE(レッドマリン)」です。
他の機関車との大きな違いは、ディーゼルを原動力にして電気を発生させ電気モーターを駆動して動かす次世代モデルという点。

走行音が静かで操作もしやすいとのこと
ちなみに愛称は導入時に社内公募し、秋葉さんが考えた「RED MARINE」に決定したそうです!

機関車や貨車のメンテナンスも千葉貨物駅の車両区で行われます。
貨車は90日ごとに検査が必須で、その方法は約100カ所を点検ハンマーで叩いて異音がしないか確認するというもの。検査員には独自の等級制度を設けており、1級に認定されたベテランの社員が検査を担当します。

一方で機関車は72時間に1度の「仕業検査」、さらに90日に1度の「交番検査」、3年に1度の「重要部検査」、6年に1度の「全般検査」を実施し、安全管理を徹底。
なかでも「全般検査」は最も大規模で、エンジンなど各部品を分解し、メーカーに送って検査をしてもらいます。検査を終えた部品を組み立てるのもここ「千葉貨物駅」です。
豆知識も教えていただきました。

写真のコンテナ車の数字の上に書かれた「コキ」の文字。「コ」はコンテナ、「キ」は表記荷重の意味とのこと。「ム・ラ・サ・キ」の記号で積載荷重を表しているそうです。
京葉臨海工業地帯の発展と共に歩んだりんてつの歴史
川崎製鉄(現・JFE)が1951(昭和26)年に千葉製鉄所を開設したのを機に臨海部の埋め立てが進み、大企業の進出が相次いだことで、千葉市~市原・袖ケ浦市に京葉臨海工業地帯が造成されました。それに伴い、日本国有鉄道(当時)や千葉県、進出企業が出資をして1962(昭和37)年に設立されたのが京葉臨海鉄道です。
設立当時は蘇我~浜五井(当時)間のみの運行でしたが、少しずつ延伸して2023年5月現在は合計9駅、営業キロ数は23.8㎞。
1978(昭和53)年3月から1983(昭和58)年までは、成田空港へ航空用のジェット燃料を運んでいたそうです。
今では、京葉線高架下の開発事業として店舗や事務所、駐車場の運営、さらに集合住宅や物流施設の賃貸といった不動産事業にも力を入れています。
沿線には鉄道マニア垂涎の名所も
歴史ある路線だからこそ、沿線には鉄道好きにはたまらない名所もあります。
例えば、前川駅~椎津駅間の「出光4号踏切」は、遮断棒が12本もある珍しい踏切として知られています。
また、千葉貨物駅~市原分岐点間に架かる「村田川橋りょう」は、1911(明治44)年に米・アメリカンブリッジ社で製作された歴史ある橋。もともとは、旧国鉄東海道本線の大井川橋梁の上流側で上り線の橋梁として使用されていたものですが、1963(昭和38)年に京葉臨海鉄道に再架設されました。
全国的にも貴重な橋梁として、2018(平成30)年に土木学会選奨土木遺産にも認定されています。

安全・正確さの裏には多くの仕事人がいた!
普段から通勤や通学に使う旅客列車とは違い、あまりなじみのない貨物列車。ですが今回、石井さんと秋葉さんのお話や千葉貨物駅の見学を通して、私たちの暮らしに密接に関わる大切な路線であることを実感しました。
そして暮らしを支える物資を必要な人の元に正確に届けるその裏には、24時間体制で仕事に向き合う多くのプロフェッショナルたちがいました。
今後、蘇我駅でマリンブルーの貨物列車を見かけたら、心の中で大きく敬礼をしたいと思います。
京葉臨海鉄道 HP http://www.rintetu.co.jp/
こちらの記事もおすすめ