旧石器時代から江戸時代までの町の歴史を考古学的な視点から解説した「目で見る酒々井3万年の歴史」が中央公民館で展示されています。
貴重な出土品もあり、イラストで分かりやすく説明しています。
公開 2023/07/03(最終更新 2023/06/29)

ソバ
大手新聞社の記者を続け、定年延長も終わったので、地域の話題を取材したいと、地域新聞様にお世話になっています。明るく、楽しく、為になる話題を少しでも分りやすく紹介したいとネタ探しの日々です。子どもの頃から麺類が好きなのでペンネームにしました。
記事一覧へ墨古沢遺跡は人が集まる交流拠点だった

約3万8千年前の旧石器時代から江戸時代に至るまで、酒々井町にはほぼすべての時代の人間の営みの跡(遺跡)が残されていて、その数は100カ所を超えます。
今年3月から酒々井町中央公民館ロビーで展示されている「目で見る酒々井3万年の歴史」では、大きな歴史の流れを上のパネルで説明、下の展示ケースには多くの出土品が並んでいます。
中でも国指定史跡である旧石器時代の墨古沢(すみふるさわ)遺跡は、写真とイラストで詳しく解説。
住居は円形に並び、120〜150人ほどが生活していた様子がうかがえます。
当時の日本列島の人口を3500〜5000人と推定すると、「墨古沢は日本の中心だったと言ってよいほど、人が集まる交流拠点だった」と解説しています。

平安時代の陶器完形の二彩椀は初出土
全国的に貴重な出土品もあります。
古墳時代の円形の古墳である飯積上台(いいづみうえだい)1号墳からは、関東地方で出土することが珍しい蛇行剣が確認されました。
蛇行剣は刃が真っ直ぐではなく、曲線状に蛇行しています。
戦う道具としてではなく、祭祀的な意味合いを持つそうです。
また古墳に埋葬された死者の枕として使う石枕も展示されています。

平安時代では二彩椀(にさいわん)という高級で特殊な陶器が出土。

発掘調査でほぼ完形品が出土したのは全国初で、貴重な品として会場にはレプリカを展示しています。
室町時代では悪霊よけのまじないの道具である木製呪符円盤(もくせいじゅふえんばん)や和鏡などが納められたつぼが見つかっています。
展示を見た人は「出土品の使用方法が描かれたイラストが分かりやすい」とのこと。
例えば弥生時代、布を織るために糸をよるのに使う土製紡錘車(ぼうすいしゃ)を使っている様子や、古墳時代に日本に伝わったかまどの使い方が、ポップな字体と親しみやすいイラストで分かりやすく示されています。
同町教育委員会生涯学習課文化財班の広瀬千絵さんは「町の歴史や文化財に興味を持っていただければうれしい」と話しています。
場所/酒々井町中央公民館ロビー
住所/千葉県酒々井町中央台4ー10ー1
時間/午前9時~午後5時 ※月曜・祝日閉館
※問い合わせ
電話番号/043-496-5334
酒々井町教育委員会 生涯学習課文化財班
こちらの記事もおすすめ





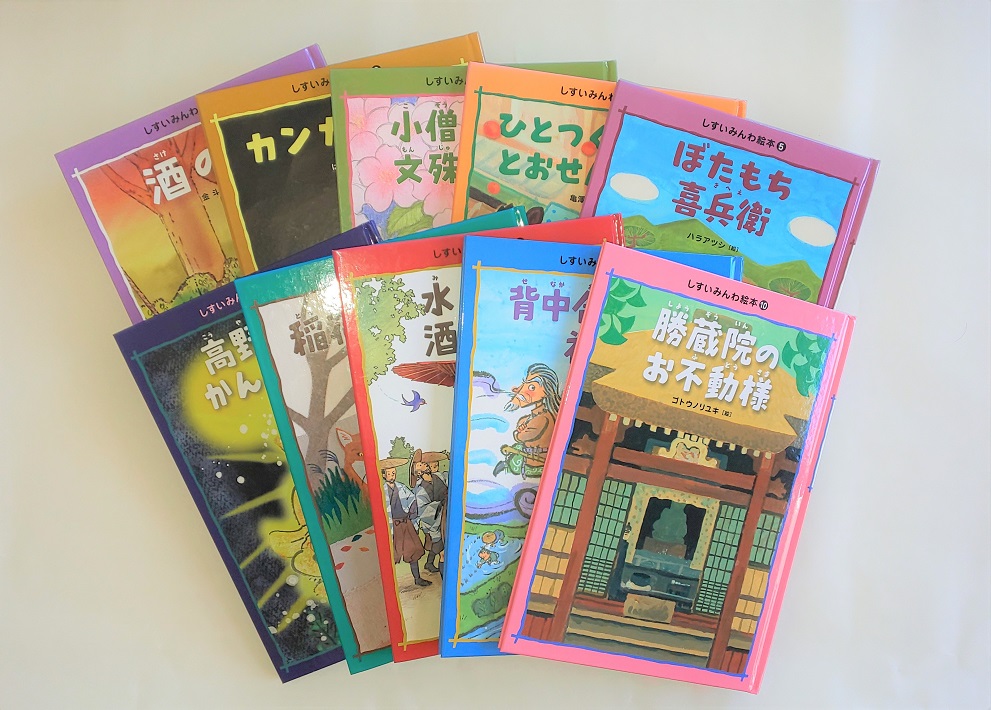






0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)









