「毎日のように姉妹でおもちゃの取り合いをしており、一緒に遊ぶことを提案したり『順番だよ』と言っても2人とも大声で泣いて伝わらない。こういう時はどうしたら?」という5歳と2歳の姉妹のママからのお悩みです。
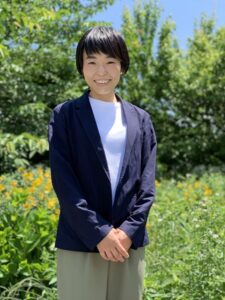
乳幼児心理学を担当。絵本を介した親子の関わりや発達を主に研究。相談者と同じ2歳と5歳の男の子を育てる2児のママでもあります。
公開 2023/09/15(最終更新 2024/02/29)

きょうだい喧嘩は子どもの成長過程において大事な学びの機会、焦って介入しないで

おもちゃを取り合うなどの子ども同士のけんかやトラブルは、多くが相手への興味や好奇心からくるもの。そして、そういった取り合いや言い合いを通して、お互いの思いに気づくことで、我慢をしたり、お互いの妥協点を見いだそうとしたりする気持ちにつながります。
けんかは子どもの成長過程において社会性を身に付ける大事な学びの機会。つい焦って介入したくなってしまいますが、止めたい気持ちをグッと抑え、まずは見守り、大人自身も子どもたちの気持ちを理解しようとすることが大切です。
子どものきょうだい喧嘩は「分かってもらえた」その安心感が解決につながります

感情がヒートアップして、子どもたちだけでの解決が難しそうな場合は介入が必要です。この時、一緒になって感情的にならないよう注意しましょう。
ゆったり優しく「どうしたの?」などと声をかけ、背中をさすったり手を握ったりスキンシップをしながら、まずは子どもたちの気持ちを落ち着かせてください。そして、それぞれの思いを否定せずに受け止め、分かりやすい言葉にして「気持ちの橋渡し」をしてから、今回のように解決策を探すお手伝いをするといいかもしれません。
事態を早く収拾したい気持ちから、上のお子さんに「お姉ちゃんだから」と妥協を求めがちですが、これは逆効果。自分の気持ちが「分かってもらえた」と安心感を得ることで、特に上のお子さんは自分から譲ったり、良い解決方法を提案してくれたりすることもあるでしょう。
最後に、年齢差がある場合は遊びのイメージのズレがけんかの原因という可能性も。時には「どんなふうに遊ぶのか見てみようか」などと声をかけて、下のお子さんを抱き、期待感を持たせながら上のお子さんのやりたい遊びを一緒に見守ってみるのも良いと思います。下のお子さんにとっても刺激になり、二人での遊びの世界が広がるきっかけにもなるかもしれません。
こちらの記事もおすすめ

















