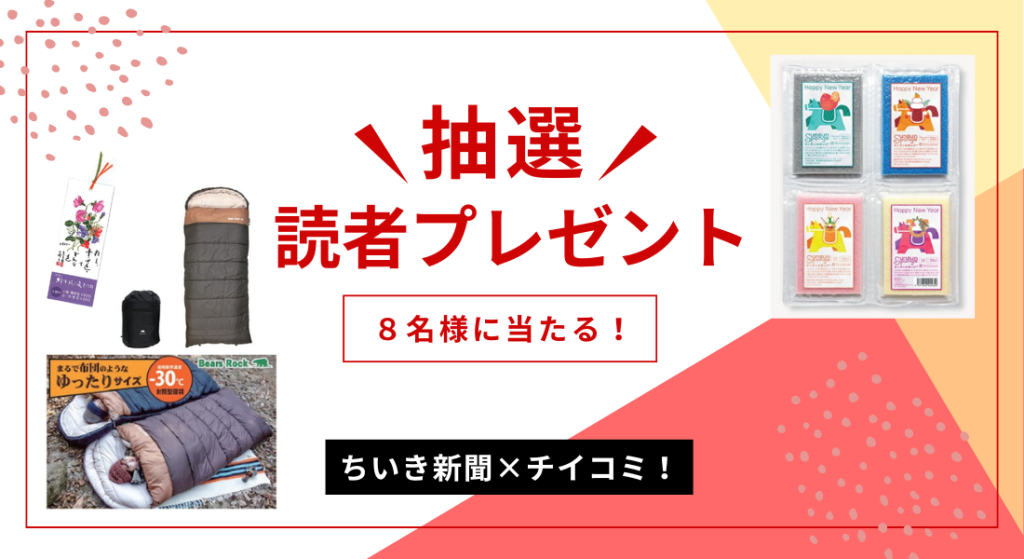子どもたちの居場所や地域のコミュニティーの場として機能する地域食堂・子ども食堂。
関係する個人・団体の交流会が実施されました。
公開 2024/01/29(最終更新 2024/03/25)

編集部 モティ
編集/ライター。千葉市生まれ、千葉市在住。甘い物とパンと漫画が大好き。土偶を愛でてます。私生活では5歳違いの姉妹育児に奮闘中。★Twitter★ https://twitter.com/NHeRl8rwLT1PRLB
記事一覧へ市内で機運の高まりを感じて開催

「四街道市みんなで地域づくりセンター」主催による「地域食堂・子ども食堂交流会」が昨年12月、四街道市文化センター(四街道市大日396)で行われました。
開催のきっかけについて「四街道市みんなで地域づくりセンター」担当者は「当センターに地域食堂・子ども食堂に関する相談が増えてきたことから、市内での機運の高まりを感じ、今回の会を設けることになりました」と話します。
既存の団体にとっては活動のモチベーションアップに、これから始めたい人にとってはノウハウを得る機会になることも期待。
当日は、地域食堂・子ども食堂に興味や関わりのある個人・団体、行政の担当者など20人以上が参加し、活発に意見を交わしました。

社会的にも重要な役割を果たす
この日、テイクアウト形式の子ども食堂「旭ヶ丘みらい食堂」を運営する長谷川晃一さんからの事例紹介も。

立ち上げやこれまでの経緯といった実体験を交えたトークに、他の参加者から資金調達や調理について具体的な質問も飛び出し、有意義な時間となったようです。
地域に広く開かれた地域食堂・子ども食堂は「本当に貧困家庭の支援につながるのか」という批判の声が少なからずあるとのこと。
それに対し、「対象を狭くすると、『貧困』というレッテルを張られることを恐れ、当事者は来てくれない。『なんだか楽しそうな場所がある』と自然と子どもたちが集まれることが大切」と数人が意見を述べ、参加者一同深くうなずく場面も。
今年、子ども食堂の開設を目指す鈴木未乃里さんは「地域食堂・子ども食堂の社会的な意義を改めて実感でき、他の団体さんとつながれる貴重な時間となりました」と参加した感想を話してくれました。
貧困や虐待、ヤングケアラーなど、子どもたちを取り巻く問題は外からは見えづらいもの。
それらをすくい上げる場所としても、地域食堂・子ども食堂の役割は大きいといわれています。
こうした取り組みをきっかけに、一人でも多くの子どもの未来が明るくなることを願います。

※問い合わせ
電話番号/043-304-7065
メール/info@minnade.org
四街道市みんなで地域づくりセンター