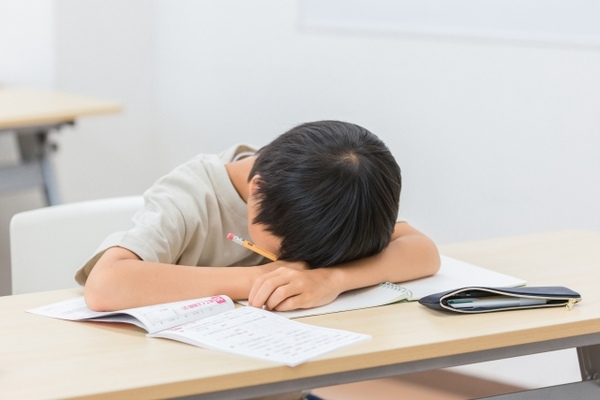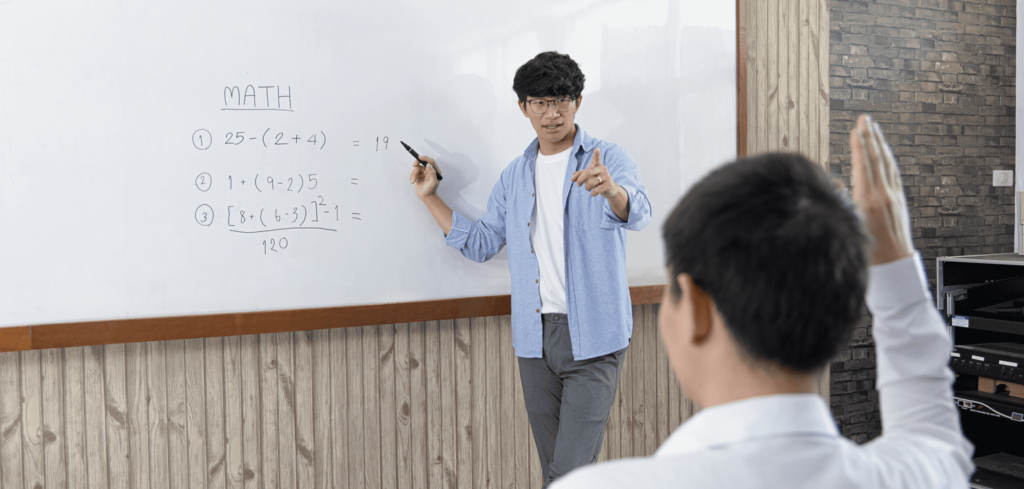塾に通っていても思うように成績が伸びないとき、このままでいいのだろうか?と思うことがありますよね。特に受験が近づいてくると、もっと偏差値を上げたいと焦ることもあると思います。
そんな時、今通っている塾にプラスして、別の塾にも通う「塾の掛け持ち」を考えるかもしれません。しかし無闇に通う塾を増やすだけでは、あまり成果は期待できないでしょう。
塾の掛け持ちは効果的なのか、二つ掛け持ちするならどんな風に選べばよいのか、気になるところを解説していきます。
公開 2022/11/28(最終更新 2025/09/11)

目次
塾の掛け持ちをしている子どもの割合
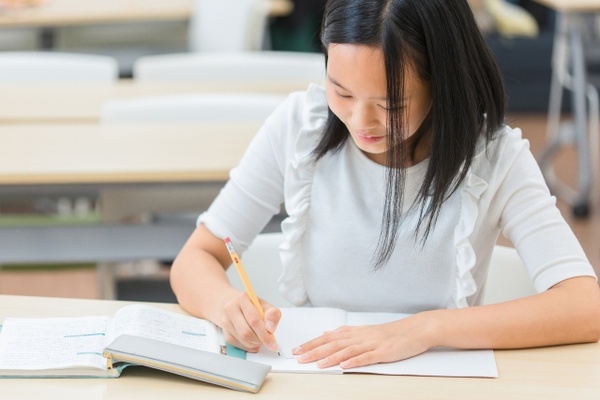
まず、実際に塾を掛け持ちしている子どもはどれくらいいるのでしょうか。残念ながら、学習塾(進学塾、補習塾、個別指導等)を複数掛け持ちしている子どもの割合について、今のところはっきりとした大規模な調査は行われていません。
そこで、これまでに行われた調査の中から、参考になるものをご紹介したいと思います。
まず、ベネッセ教育総合研究所が2017年に実施した「学校外教育活動に関する調査」によると、学習塾(進学塾・補習塾)に通っている子どもの割合は以下の通りです。
・小学生 進学塾7.3%、補習塾5.3%
・中学生 進学塾31.7%、補習塾13.4%
・高校生 進学塾20.8%、補習塾5.1%
塾の掛け持ちに関しては、平成20年の古いデータですが、文部科学省による「子どもの学校外での学習活動に関する実態調査報告」が参考になります。この調査で、小学生・中学生を対象に「学校外で何らかの学習活動をしている者のうち複数の異なる種類の学習活動をかけもちしている割合」が明らかにされています。割合は以下の通りです。
・小学1年生〜中学1年生40%前後
・中学2年生35.9%
・中学3年生31.3%
ただし、ここでいう「学習活動」は、学習塾・家庭教師・通信添削・習い事(ピアノ、そろばん、習字など)をすべて含んでいます。この数字には「塾とピアノ教室に通っている」「ピアノと習字に通っている」といった子どもが多く含まれていることが予想されます。
そういったパターンを含んでこの数字ということは、学習塾を掛け持ちしている子どもの割合は数値としてはそれほど大きくないと推察できるでしょう。塾を掛け持ちしている子どもは、大学受験・高校受験・中学受験とどの年代に関しても難関校の受験を目指している場合も多いため、他と差をつけるための手段のひとつと言えるかもしれません。
塾を掛け持ちすることのメリット
そもそも、塾は一か所に通っていれば十分ではないのでしょうか。わざわざ掛け持ちして複数の塾に通うことのメリットを紹介します。
苦手科目を重点的に学習できる
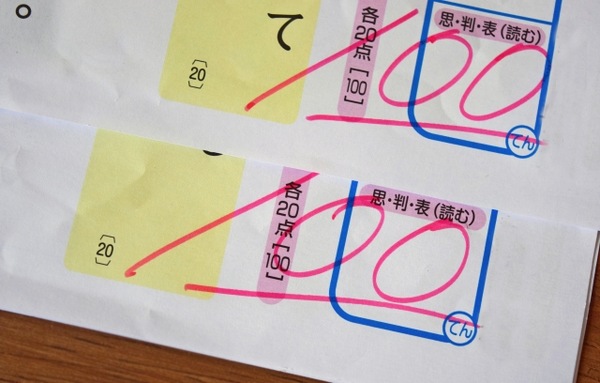
まず、塾を掛け持ちすることの大きなメリットに、苦手科目の重点的学習ができる点があります。子どもたちにはそれぞれ、得意な科目もあれば苦手な科目もありますよね。得意な科目は集団授業で十分だけれど、苦手科目は内容の理解が追いつかないという子どももいます。
たとえば数学は得意だけれど英語が苦手という子どもの場合。数学は進学塾で集団授業を受講して、英語は個別指導の他塾、または集団授業+個別指導の併用という形にできます。そうすると、苦手科目にはゆっくり向き合って重点的に弱点を克服していけるため、手厚い対策が可能になります。
また、英語の強化は英語を専門とする英会話教室へ通うというように、特色・得意分野によって塾を使い分ける方法もあります。つまり得意科目・苦手科目それぞれに、必要な学習スタイルに合った塾を選ぶのは、塾の掛け持ちとして有意義なパターンと考えられるでしょう。ただ何となく不安だからと、全教科を2つの進学塾で受講するような形は負担が大きく、おすすめできません。
もう一つの塾のフォローができる
塾の掛け持ちでもっとも多いパターンは、おそらく進学塾(集団授業)+個別指導塾の組み合わせだと思います。その中には、一方を完全にメインの塾をフォローするために使う方法もあります。
たとえばメインで通っている大手予備校だけでは講義のスピードが速くてついていけない、進学塾の集団授業についていけない、といった場合も、個別指導塾を掛け持ちしていれば、わからなかったところは後日ゆっくり講師に教えてもらうこともできます。
反対に、個人に合ったきめ細やかな指導が期待できる個別指導塾をメインに据えて、受験関連の情報量を多く持っている進学塾の夏期講習や志望校別特訓の講座をプラスするという方法もあります。
どちらの場合でも、メインの塾で学んだことをより充実した形で身につけることが期待できるでしょう。
ただし、こういった「サブの塾として通いたい」という利用方法が可能かどうかは、あらかじめ確認が必要です。個別指導塾の中には他塾の教材等を持ち込んでの質問を嫌う場合もあり、進学塾の特別講習においても、平常からの受講生のみを対象とする場合が多くあります。
塾を掛け持ちするのなら、目的に合った通い方ができることを重視しましょう。最近は、メインの塾をフォローするためにオンライン授業を受講する子どもも多いようです。
一つの塾では足りない部分があるのなら、その足りない部分を効率的に補える方法を探すと失敗がないでしょう。
塾を掛け持ちすることのデメリット
それでは、塾を掛け持ちすることによるデメリットは何でしょう。たくさん勉強すればするほど良いような気もしますが、やはりそこまで単純ではありません。こちらについても検討してみたいと思います。
子どもの精神的負担
まずデメリットとして考えられるのは、子どもの精神的負担が増加することです。子どもたちは毎日学校へ通っている上での通塾ですから、その上複数の塾の掛け持ちとなると、体力的にも精神的にも疲れ切ってしまうかもしれません。
時間数が増えないとしても、新しい環境に馴染むのが苦手な子どももいます。あちこちへ通うと、それぞれの場所でそれぞれの先生や生徒との人間関係が発生し、負担を感じる子どももいます。塾の掛け持ちには、子ども自身の性格も考慮した方がよいでしょう。
指導方針の違いによる混乱
指導方針の違いによって混乱してしまう可能性も考えられます。塾によって各教科の教え方も違いますし、雰囲気(厳しめ、のんびり等)も異なります。掛け持ちしている塾の違いによって、どちらに合わせればよいのか戸惑ってしまう子どももいるでしょう。
複数の解き方を教えられると混乱してしまうようなら、塾は一つに絞った方がよいかもしれません。もしくは、メインの塾の解き方を見て、合わせて対応してくれるような個別指導塾や家庭教師を選べば混乱を防ぐことができます。
経済的負担
最後に、通う塾を増やすということは、経済的な負担が大きくなるということでもあります。一つの塾であっても、通塾にかかる費用は決して小さいものではありません。複数の塾に通うとなると、さらに費用は増大します。
教科ごとに通う塾を分ける場合でも、塾によっては2教科目以降の料金が安くなるなどのお得な料金設定がある場合もあり、その恩恵を受けることができなくなります。
また、費用以外にも、送迎などの手間や負担が増える場合もあります。
塾の掛け持ちが魅力的であっても、それだけの費用をかける価値があるのか、子どもにとって本当に必要なのか、よく検討することが大切です。
塾の掛け持ちを失敗しないために
塾の掛け持ちで失敗しないためには、なぜ必要なのか、本当に複数の塾が必要なのか、よく考えることが重要です。勉強する場所や時間を増やせば増やしただけ、成績が上がるだろうと何となく考えるのは失敗のもと。塾を掛け持ちする目的を明確にして、その目的に合った塾選びを心がけましょう。
そして、子どもと勉強の方針についてよく話し合うことも大切です。勉強するのは子ども自身ですから、大人の判断だけで、塾の掛け持ちを強制することは望ましくありません。子どもにとって最適な勉強方法を、子どもの意思に寄り添い一緒に探してあげられるとよいでしょう。
まとめ
塾の掛け持ちは、有意義に使えば非常に効果的と言えます。ただし、複数の塾に通う必要性をよく考えて、不安だけを理由に決めないことが大切です。子ども一人一人、自分に合った勉強のスタイルはそれぞれ異なります。塾の掛け持ちを決める時も、また、決めた後も、子どもの様子をよく見て、本人の声を聞いてください。
▷ 近くの塾を探す