関東ローム層と呼ばれる、水はけのよい火山灰土壌が落花生の栽培に適しているといわれ、落花生栽培が盛んな八街市。JR八街駅からしばらく歩くとたどり着く、1952年創業の「大平商店」の落花生は、パッケージを開けるとぷーんと漂ういい香りにまず驚かされます。口に運ぶと、素材の良さゆえのシンプルなうまみが舌に伝わってきて、思わずもうひとつ、またひとつと食べ進めてしまうおいしさ。その秘密を取材しました。
公開 2025/08/01(最終更新 2025/07/24)

目次
豆煎り習得に10年! こだわりの電熱加工
二代目としてお父様のお店だった大平商店を継いだ大平美東武(みとむ)さん。高校を卒業してすぐにお店の手伝いをはじめ、最初に挑戦したのが落花生の豆煎りでした。失敗すると落花生が無駄になってしまうので、お父様に「もういい。2階で寝てろ!」と厳しく怒られたといいます。「完全に習得するのに、だいたい10年はかかりました」と美東武さんは笑います。

ガスバーナーを使用する方法もありますが、美東武さんのこだわりは電熱ヒーターを使用した加工法です。落花生を均一に加熱し、素材の素直な味や、香ばしさを引き出すことができるといいます。もちろん、完成したかどうかの最終的な判断は落花生の水分量などを見て人の目で行っています。
また、品種としては千葉県で栽培される落花生の中でも、特に高級品種として知られる「千葉半立」の使用にこだわっています。
落花生の加工は主に美東武さんが担当。奥様のきよみさんが袋詰めや販売を担当し、時には息子さんやパートさんたちも手伝いに加わって、少数精鋭でお店を経営してきました。袋詰めはすべて昔ながらの手作業で行っているといいます。

看板商品のひとつ、ピーナツの甘納豆が生まれるまで

大平商店の看板には大きく「ピーナツ・甘納豆」と書いてあり、落花生の甘納豆も現在の看板商品のひとつです。ところが、この甘納豆の誕生の裏側には、嘘のような本当の話がありました。
「実は埼玉に甘納豆を作っている親戚がいて、甘納豆を扱ってみてはと言われて看板に『甘納豆』と書いたんです。そしたら看板を見たお客さんから『ピーナツの甘納豆ください』と言われるようになって、これは新商品を作らないとな、と覚悟を決めて開発しました」と美東武さん。
通常の甘納豆は小豆や金時豆を使用するため、ナッツ類である落花生を使った甘納豆はなかなかうまくいかず、何度も試作を繰り返したそうです。苦労を重ねて完成した落花生の甘納豆は、珍しさやしっとりした食感が評判を呼び、今では大平商店の人気商品のひとつです。
これからも八街の落花生を守り続けたい

落花生の仕入れ先は八街市を中心とした千葉県内の農家で、長いお付き合いが続いているといいます。世代交代もあり、農家さんの数は減っているといわれていますが、「これからも八街の落花生という地域の名産物を守るため、いい商品を作り続けていきたい」と皆さんで笑顔を見せてくれました。
高級品種の千葉半立をおいしくお届け
大平商店の看板商品をご紹介しましょう。
さや付き落花生とさや無しの素焼き、どちらがお好み?

さや付き落花生もさや無しの素焼き落花生も、どちらも味付けはなく、素材の味のみ。電熱加工でカリッと仕上がった落花生は、食感と香りと味すべて、どこまでも本物を感じさせてくれます。
収穫された落花生は人の手で選別して、洗って天日干しで乾燥した後に電熱加工を行います。さや付き・さや無しどちらもおすすめですが、高齢の方にはさやをむく手間がいらないさや無しの素焼きが人気だそう。さや付きは、自分の手を使ってさやをむく楽しみが味わえます。
しっとりした食感が新感覚のピーナツの甘納豆

カリッとした食感というイメージのピーナツが、なんと甘納豆になりました。千葉半立を数日間かけて砂糖とオリゴ糖でじっくりと煮込み、やわらかくしっとりとした食感に仕上げています。子どもやご高齢の方でも食べやすく、お茶菓子などにぴったりです。

取材担当おすすめポイント
千葉県産の千葉半立という品種にこだわり、シンプルな工程で仕上げられた大平商店の落花生。素材の良さがストレートに伝わってくるおいしさは、美東武さんの職人気質によるところも大きいのだろうなとお話を聞いていて感じました。早くからパソコンを手に入れて、今ではお客さまの管理システムや会計システムなどを構築しているといいます。丹念な研究によってたどり着いた、独自の製法で作られた落花生は贈り物にもぴったりです。

大平商店
住所/八街市八街ほ835-25




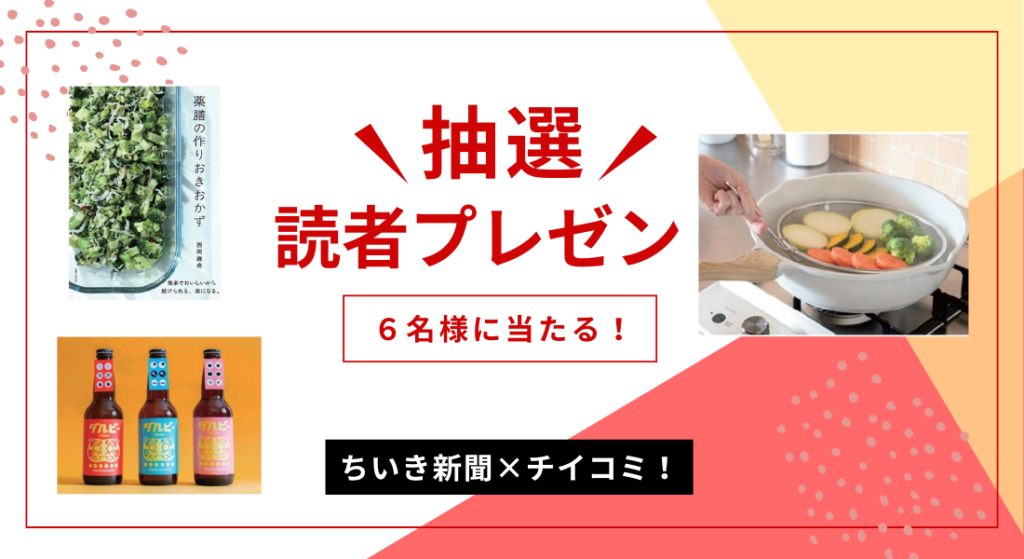








0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)









