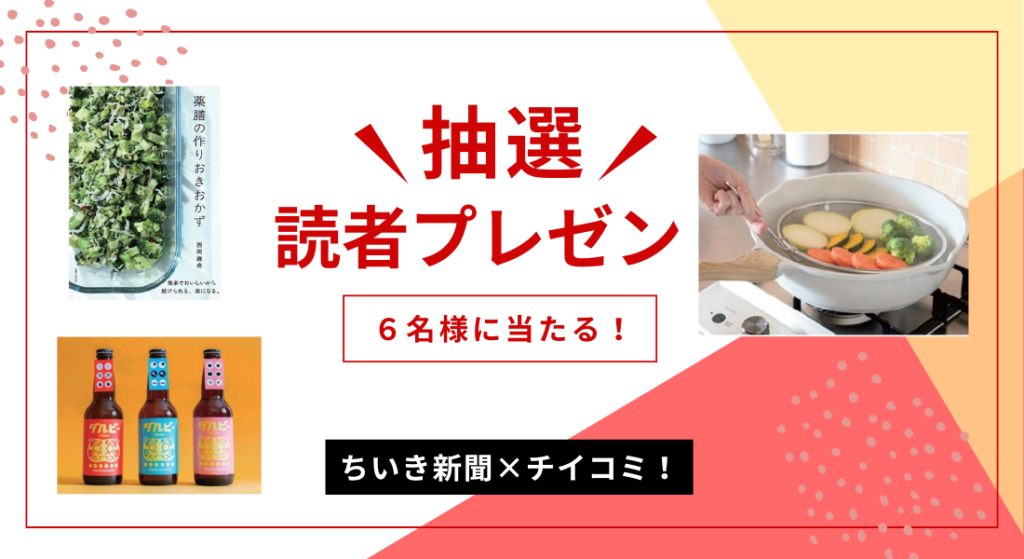ライフスタイルや好みに応じた補聴器を選べば充実した毎日に。
選び方のこつを「聞こえのプロ」に教えてもらいました。
お話を聞いたのは

かなで補聴器代表
認定補聴器技能者 岡田恵子さん
外資系臨床検査会社、補聴器販売会社を経て2018年に独立。2022年認定補聴器専門店として公益財団法人テクノエイド協会による資格審査に合格する。
公開 2025/09/10(最終更新 2025/09/09)

見た目も機能も進化した補聴器
聞こえづらさを自覚していても、補聴器の使用に抵抗がある人は多いようです。
理由の一つは見た目。ところが最近では、さまざまな種類があり、デザイン性もアップ。
豊富なカラーバリエーションや目立ちにくいデザインなど、選ぶ楽しさがあります。
もちろん見た目だけでなく、機能面でも目覚ましい進化が。
AI搭載やスマートフォンとの連携など、どんどん便利になっています。
伴走してくれる専門家から購入を
補聴器を購入したものの、使用感に不満があり、しまい込んでしまっているという話も聞きます。
実は補聴器の使用に慣れるまでは、快適さよりも煩わしさが上回ります。
聞こえ方は一人一人違うもの。
専門店ではスタッフが使用者に合わせて利得・音質・出力を調整しますが、初めは自分の声が響き、慣れるまでは3か月程かかります。
購入後のアフターケアはとても重要です。
例えば当店では、お客様の使用状況をログデータで確認、その上で音場効果測定を行い客観的に評価して音を調整(フィッティング)します。
お客様の使い心地をとても重視しています。
価格だけではなく、知識と経験のある認定補聴器技能者が常駐している認定補聴器専門店で、予算と機能、使い勝手において本当に納得できる商品を選ぶことが、満足度につながるといえます。
難聴の原因はさまざまなので、補聴器購入の前に、耳鼻科の受診を。
受診の目安は、聞こえないことで生活に支障を来しているかどうか。
本人だけでなく家族や周囲の人が不便を感じているかも判断基準になります。
特に「音は聞こえるけど言葉の意味が分からない」という場合は注意が必要です。
言葉が理解できないとコミュニケーションがうまくできず、人付き合いが面倒に。
最近では難聴と認知症の関係性に関する話題も多いですが、趣味に仕事にと、いくつになってもアクティブに人生を楽しんでいる人ほど、補聴器を愛用しています。
聞き間違い例
● 白い→広い
● 1時→7時
● 佐藤さん→加藤さん
● スイカ→いか
補聴器の種類
耳かけ型
パワー重視の「BTE」 軽い付け心地の「RIC」2タイプあり

耳あな型
耳の形に合わせたオーダーメイド品が主流(レディメイドもあります)。
トレンドは充電式(Li-ion)
電池交換不要で操作も簡単な「耳あな充電式補聴器」の種類が増えています。

Q.購入金額の目安は?
機能や性能によって異なり、片耳で13~60万円、およそ両耳で28~140万円と幅広い価格帯の商品があります。補聴器は医療用具のため、消費税はかかりません。
Q.助成金制度とは?
補聴器購入前に、耳鼻科を受診し、治療を目的とした補聴器購入は医療費控除の対象になる場合があります。また、自治体によっては購入時に補助金が出る場合も。
Q.耐用年数は?
一般的に5年が目安といわれています。長持ちさせるにはお手入れが肝心。メンテナンスもしっかり行ってくれる販売店で購入すると安心です。
Q.高価なものほどいいの?
一概に言えません。価格にかかわらず本人が快適に使えるかが大切です。
補聴器選びの流れ
1.耳鼻科受診
補聴器適合に関する診療情報提供書を専門店へ
2.カウンセリング
聞こえにくい場面や耳鼻科の受診の有無、使ってみたい補聴器などご希望を伺います
3.聴力測定(音場効果)
音の聞こえ方 言葉の聞き取りテストなどを行います
4.機種選び
情報提供書、測定結果ご予算、お客様のご要望を踏まえて機種をご提案
5.視聴
補聴器の装用練習 付け心地をチェック
6.購入
家計を伴にするご家族の同意を確認
7.装用トレーニング
1カ月ほど小さめの音で自声に慣れるまで伴走
8.アフターケア
定期的なメンテナンス、フィッティング
故障・紛失に注意を!
ポケット…うっかり洗濯
マスク…からまって落下
ペット…かみ砕き
ティッシュ…ごみと間違われて廃棄