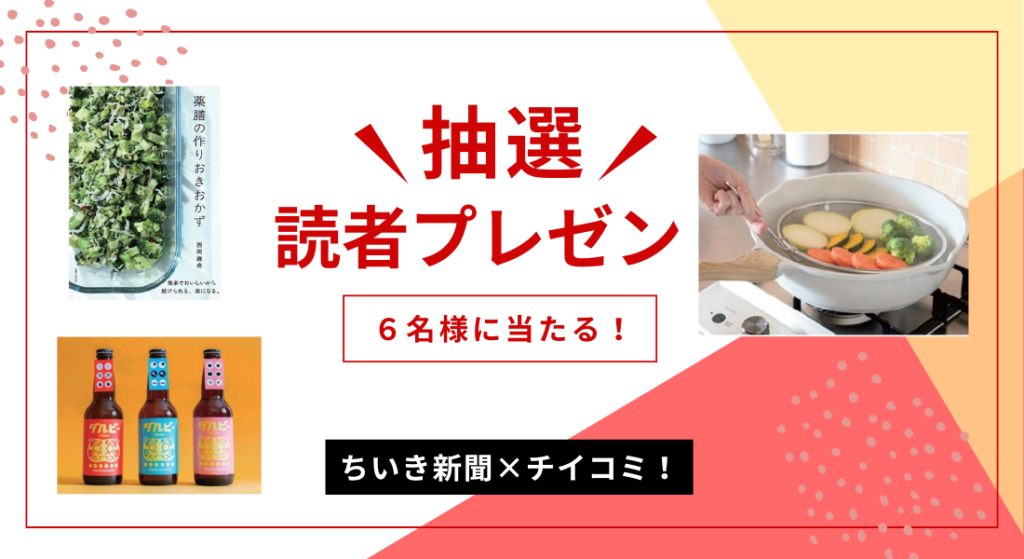県北西部にある手賀沼はかつて水草の宝庫でしたが、水質悪化などで沈水植物(水草)が絶滅。しかし、水槽で土着株を再生し復活させる取り組みが進んでいます。
公開 2025/09/27(最終更新 2025/09/22)

ソバ
大手新聞社の記者を続け、定年延長も終わったので、地域の話題を取材したいと、地域新聞様にお世話になっています。明るく、楽しく、為になる話題を少しでも分りやすく紹介したいとネタ探しの日々です。子どもの頃から麺類が好きなのでペンネームにしました。
記事一覧へ絶滅した水草を復活へ
沈水植物は水底に根を張り、葉を水中に広げていますが、水が濁ると光が届かず光合成ができません。
一方で、ミジンコなどアオコを食べるプランクトンの隠れ家となり、水生昆虫や魚、鳥を呼び寄せ、生き物のにぎわいを生み出します。
手賀沼では1970年代後半、水質悪化や浅瀬の減少により沈水植物が絶滅。
当時は生活雑排水の流入が主原因とされていましたが、現在は下水道整備や合併処理浄化槽の普及で水質が改善しています。
沈水植物のガシャモクは沼底の土壌に休眠していた種からの発芽に成功し、栽培が進行中です。
夏場の高水温や水位低下が課題で、掛け流しや水の補充で対応します。
アオミドロが絡んだ場合は手で取り除きます。
休眠の種を再生し栽培に取り組む
手賀沼流域7市の市民団体と行政、県で構成する「手賀沼流域フォーラム実行委員会」では、手賀沼由来の沈水植物ガシャモクの水槽栽培を市民に勧めています。
8月には印西市で親子向けワークショップが開催。
大きなたるに、鉢植えの水草と水を入れて育てます。



参加した小学3年生の男児は「大事に育てて増やしたい」と話していました。
現在の水質は水草が繁茂できる状態で、アメリカザリガニによる食害が抑えられれば、水槽で育てたガシャモクを移植することによる本格的な復活も期待されます。
問い合わせ
メール/teganumaform@yahoo.co.jp
手賀沼流域フォーラム実行委員会