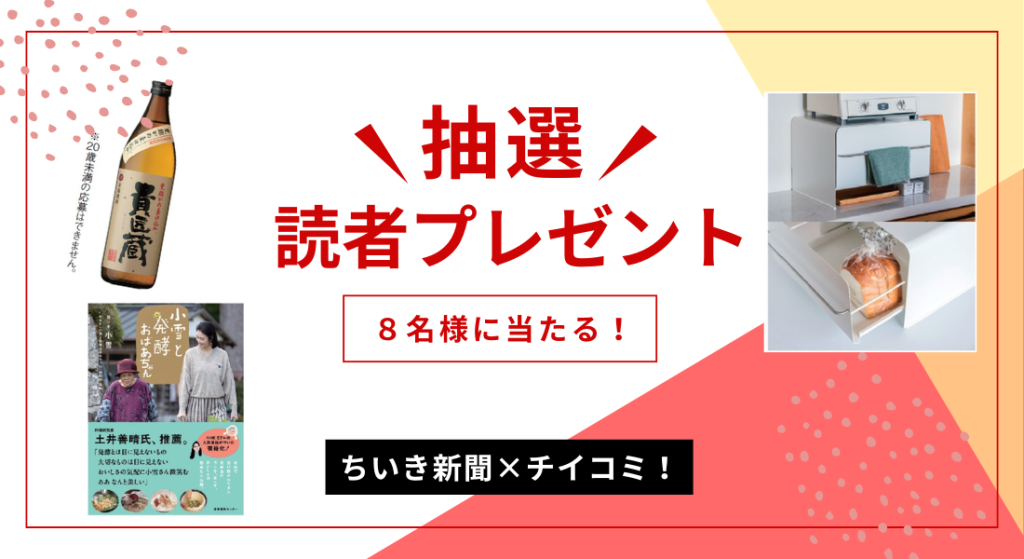「羊を数えると眠れる」「寝る前のスマホはよくない」「お酒を飲むとぐっすり眠れる」――こんな睡眠の都市伝説を耳にしたことはありませんか? でも実際のところ、どうなのか気になりますよね。
今回は江戸川大学睡眠研究所の山本隆一郎教授に解説いただきながら、睡眠にまつわるウソ・ホントをQ&A形式でご紹介します。ちょっとした噂の真実を知ることで、ぐっすり眠るためのヒントが見つかるかもしれません。都市伝説に惑わされず、今日から試せる快眠法をチェックしてみましょう。
お話を聞いたのは…

公開 2025/10/22(最終更新 2025/10/22)

Q1. 羊を数えると本当に眠れるの?
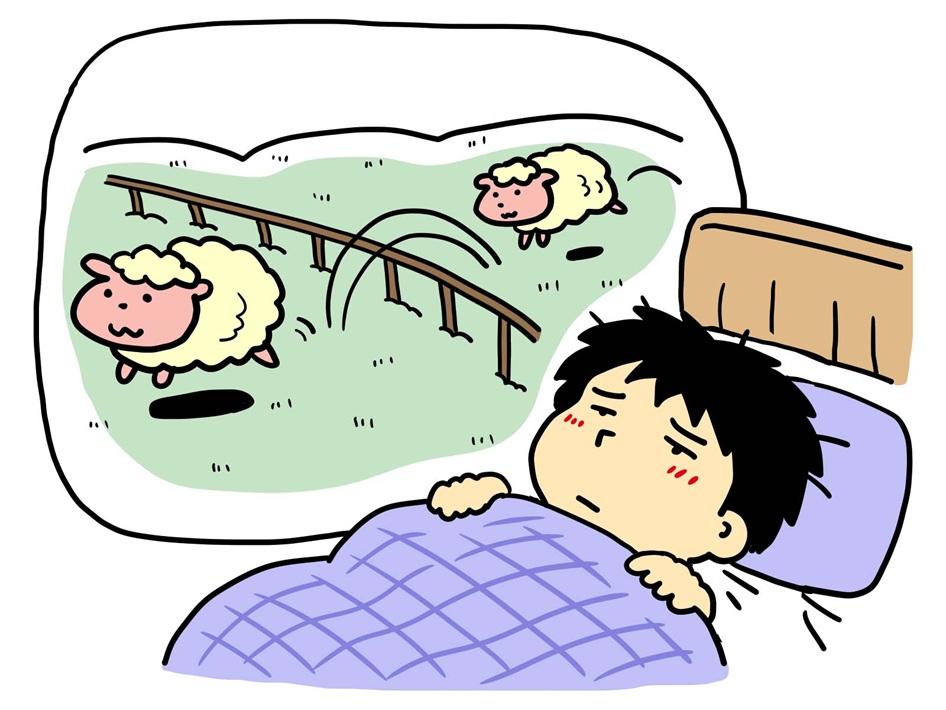
羊を数えても眠りには効果がありません。そもそも眠るために寝床で何かしようとすること自体が覚醒を高めてしまいます。さらに、羊が1匹、2匹…と数え続けるうちに、自分が眠れていないことを意識して不安を強めてしまいますね。
Q2. 寝る前のスマホは眠りを妨げる?

寝床でのスマホは控えたほうがいいでしょう。布団を「スマホで動画やコンテンツを見る場所」として習慣化してしまうと、布団と覚醒が結びつき、入っただけで目がさえてしまいます。
布団に入る前のスマホ利用についても、ブルーライトが体内時計や睡眠に影響することから問題視されることがあります。しかし実際のところ、スマホの光の影響はそれほど大きくありません。ナイトモードや画面の明るさ調整も可能ですので、光という点については過度に神経質になる必要はありません。
それよりも、寝る前の室内の照明の強さに注意しましょう。明るすぎる照明は体を覚醒させてしまいます。また、スマホでショート動画のようなコンテンツを視聴することも覚醒を高める原因になりますので、寝る前には控えた方がよいでしょう。
Q3. お酒を飲むと眠りやすくなる?

眠るためにお酒を飲む、いわゆる「寝酒」は絶対におすすめしません。お酒には入眠を促す効果がありますが、利尿作用や代謝産物のアセトアルデヒドが覚醒を高めるため、中途覚醒につながります。また、呼吸生理にも影響を与え、睡眠時無呼吸のリスクを高めることもあります。
寝つきをよくする目的で飲むお酒は、結果的に睡眠全体の質を下げてしまうのです。また、アルコールの入眠効果に対する耐性はすぐにできてしまい、数日で量が増えてしまう傾向があります。その結果、アルコール依存につながる危険性もあります。
Q4. 寝だめで睡眠不足は解消できる?
寝だめはおすすめできません。休日に長く寝ても、平日の睡眠不足を完全に補えるわけではありません。
むしろ、平日との睡眠スケジュールの差が大きいと体内時計が乱れ、家にいながら時差ボケのような状態になって調子を崩してしまいます。平日も休日も同じような睡眠リズムを保つことが大切です。
Q5. 昼寝をすると夜眠れなくなる?
午後の早い時間に短めの昼寝(成人なら15分程度、高齢者なら20分程度)は夜の睡眠にほとんど影響せず、日中の覚醒を維持するために効果的であることが実験研究から報告されています。
ただし長く眠ると、起床後のぼーっとした感覚(睡眠慣性)が出たり、夜の眠りが浅くなったりすることがあります。日中の眠気対策として昼寝に頼るのではなく、夜に十分な睡眠時間をとることが最も大事です。
Q6. 金縛りは霊の仕業?

金縛りは霊の仕業ではありません。金縛りの正体は、眠り始めのレム睡眠(入眠レム睡眠)です。眠りに入ってすぐは浅いノンレム睡眠から深いノンレム睡眠に移行し、そのあとでレム睡眠が現れますが、寝入りばなにレム睡眠が起きると、睡眠麻痺、いわゆる金縛りが生じます。
レム睡眠のときには運動神経が抑制され筋肉が弛緩します。さらに、不安などに関わる脳の部位の活動が活発になることもあり、幻覚体験や怖い映像・音の感覚が伴うことがあります。睡眠覚醒リズムが不規則だったり、長い昼寝の後だったりすると金縛りが起きやすくなります。
実際に多くの人が体験していて、調査では日本の青年の約8%が「過去1か月以内に金縛りを経験した」と答えています。珍しいことではなく、心身のリズムの乱れが関係しているのです。
Q7. 早寝早起きは本当に健康に良い?
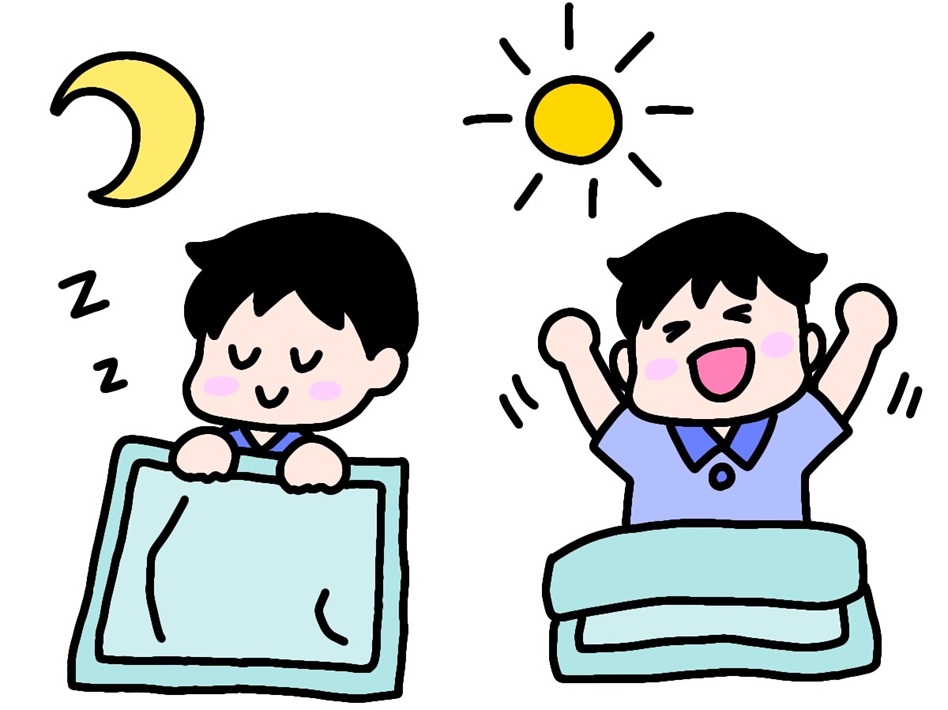
必ずしも「早寝早起き」が体によいとは限りません。重要なのは、毎日同じ時刻に起床して体内時計のリズムを崩さないことです。
週末や休日に、夜遅くまで起きていたり、朝遅くまで眠っていたりすると体内時計が乱れ、体調不良につながります。起きる時刻を固定し、夜に一度連続した睡眠を規則正しくとることが健康には大事です。
Q8. 夢は眠りを妨げることがある?
夢そのものが眠りを妨げるわけではありません。人は一晩の睡眠で何度も夢を見ていますが、多くの場合、夢を見たことを覚えていません。
ただし、ストレスがあると夢を覚えていることが多くなります。夢を見ること自体が原因ではなく、夢をよく見たと感じるときはストレスや生活習慣の乱れ、睡眠リズムの乱れが背景にあることが多いです。
Q9. どんな寝姿勢が睡眠にとってよい?
眠る姿勢で睡眠が促進されたり妨害されたりすることはあまりありません。睡眠中に何度も寝返りを打つためです。
ただし、閉塞性睡眠時無呼吸がある場合は仰向けだと無呼吸が起きやすく、横向きがよいでしょう。また、腰痛がある場合はうつぶせ寝が症状を悪化させることもあります。最適な寝姿勢には個人差があります。
Q10. 眠れないときは1回起きるのがいい?

これはその通りですね。眠れない状態で布団にいると、布団=眠れない場所と体が学習してしまいます。これを条件づけといいます。
例えば梅干しを食べたことがある人は、見るだけで唾液が出ますね。同じように、不眠の状態を体が覚えてしまうと、布団に入っただけで目がさえてしまいます。眠れないときは一度起きて、別のことをしてから再度寝るのが有効です。
Q11. 悪夢を見ることにはメリットがある?
夢自体にメリットもデメリットもありません。夢はレム睡眠中によく見ているとされますが、レム睡眠中は恐怖や不安に関わる脳の部位が活性化しています。そのため、夢は焦りや不安を感じるような悪夢であることが多いです。
Q12. 「寝る子は育つ」は科学的に正しい?

「寝る子は育つ」は正しいと言ってよいでしょう。睡眠前半に多く出現する深いノンレム睡眠中に成長ホルモンが分泌され、骨や筋肉の成長を促します。
また睡眠は記憶とも深く関わり、手続き記憶(運動や動作の記憶)の定着に役立ちます。睡眠中にはシナプス(※)の刈込が促進され、機能的で無駄の少ない神経回路が構成されます。
※シナプスとは…脳の神経細胞(ニューロン)同士をつなぐ部分のこと。情報は電気信号として神経細胞を伝わり、シナプスで化学物質に変換されて次の細胞に送られます。睡眠中にはこのつながりが整理され、効率の良い神経回路に組み替えられます。
Q13. ゴールデンタイム(22時~2時)に眠ることは美容にとっていい?

「夜10時から深夜2時までは睡眠のゴールデンタイム」といった説明を耳にすることがありますが、これは科学的な根拠がありません。お肌や骨のターンオーバーに関わる成長ホルモンの分泌が理由として挙げられることもありますが、実際には成長ホルモンは体内時計に依存するのではなく、深いノンレム睡眠のタイミングで分泌されます。
さらに、体内時計には年齢や生活リズムによる個人差があります。そのため「この時間に眠れば美容や健康にいい」という一律の考え方は誤りです。大切なのは、自分の生活リズムに合わせて十分な深い睡眠をとることなのです。
Q14. 寝る間も惜しんで勉強した方がいい?
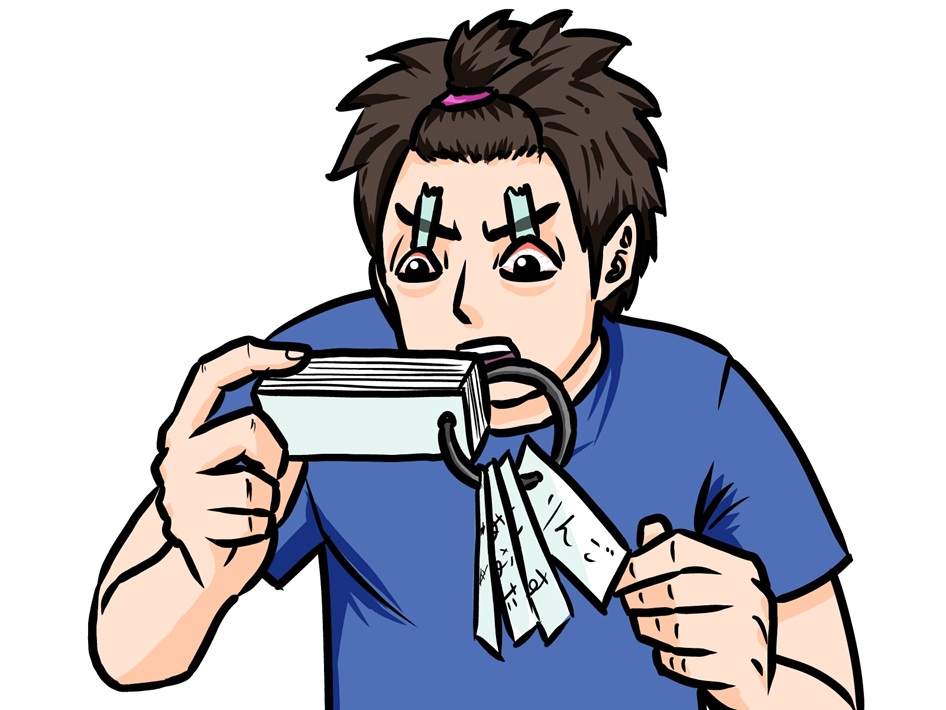
昔は「四当五落(※)」「蛍雪の功」のように、寝る間を惜しんで勉強することが良いと考えられていました。しかし睡眠不足になると、勉強したことが定着しにくくなり、成果を発揮することも難しくなります。睡眠不足により低下する認知機能は、勉強をすることや学んだことを活かすための基礎になります。
※四当五落…睡眠時間4時間なら受験合格、5時間なら不合格
Q15. ショートスリーパーって本当に実在するの?

「睡眠時間が短くても平気!」と思っている人は少なくありません。しかし、医学的に見て本当に健康に問題のない「真のショートスリーパー」は、存在したとしてもごくわずかだと考えられています。
実際には睡眠不足が続くと、認知機能の低下や眠気を自分で正しく判断できなくなり、「自分は短時間睡眠でも大丈夫」と勘違いしてしまいやすいのです。
また、深いノンレム睡眠は脳や体のメンテナンスに欠かせませんし、浅いノンレム睡眠は認知機能の回復、レム睡眠は神経回路の形成や記憶の整理に重要な役割を果たしています。これらのプロセスを十分に経るためには、やはりある程度の睡眠時間が必要です。