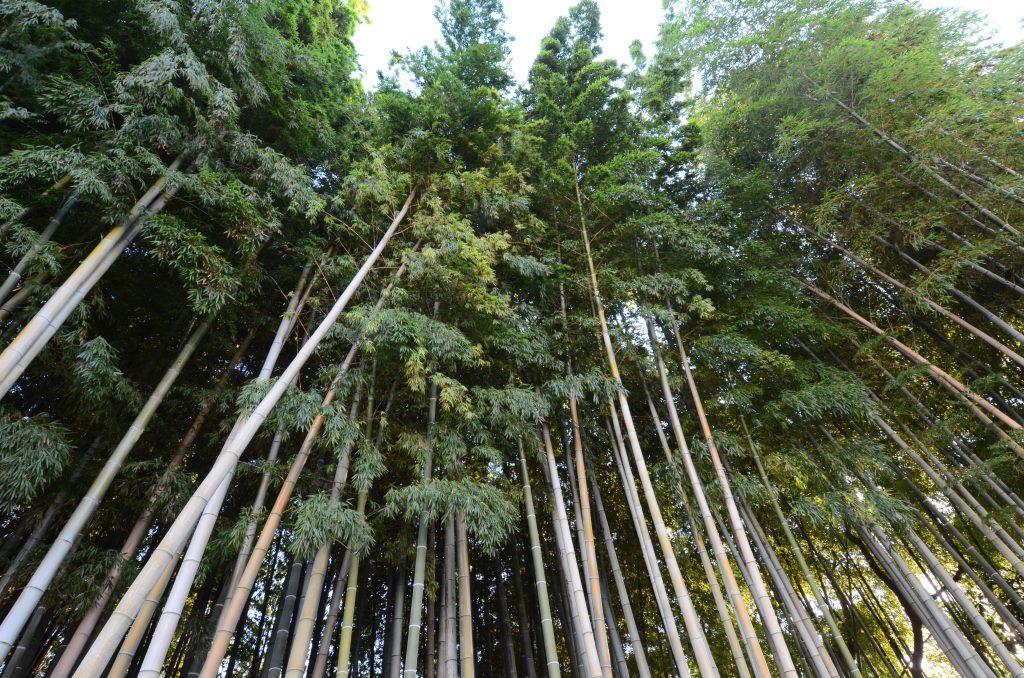セイヨウ(西洋)ミツバチと、ニホンミツバチ。
同じように見えますが、性格も生態も異なります。
古来この国に生息してきたニホンミツバチを飼育する布施達治さん(船橋市在住)に話を聞きました。

公開 2020/12/01(最終更新 2022/03/08)

おいしい蜜を分けていただく
9月中旬、小雨の降る朝、船橋市のお宅にお邪魔しました。
庭のすみに置かれたニホンミツバチの巣箱からハチミツを採る作業を見学させてもらうためです。
穏やかな表情で、ハチに優しく声を掛けながら巣箱の隙間にゆっくりとナイフを入れていく、布施達治さん。
市川市の高校で生物の教員をしながら、自宅や友人宅の庭に巣箱を設置し、ニホンミツバチを飼育しています。

布施さんがミツバチを飼育し始めたのは今から10年前、当時勤務していた高校近くの自然保護区で野生のニホンミツバチの巣を発見、生物の教材として授業に使えないかと考えたのがきっかけだといいます。
現在は、高校と自宅、友人宅に計4個の巣箱があり、「おいしい蜜をミツバチから分けてもらっている」とほほ笑む布施さん。
独特の味わい「百花蜜」とは
私たちが普段口にするハチミツは、セイヨウミツバチを管理飼育した養蜂産業によるものが多く、サクラやれんげの花から集めた蜜は均一な味わいで優秀な甘味料です。
一方、ニホンミツバチは、私たち人間が「花」と認識しないような草木まで訪れ、蜜を集めます。これが、ミツバチの集める蜜が「百花蜜」と呼ばれるゆえんです。
ニホンミツバチは、その土地特有の自然の恵み、多様な生物、植物が共に生きる環境を守る一助となっています。
そのため、「巣箱を置く場所によって味に個性があり、面白い」と言う布施さん。


地域の自然を守るニホンミツバチ
自然界では5000万年以上前からハチと植物の受粉のやり取りが行われてきたそうです。
ここ日本で、ニホンミツバチは、野山で、田畑で、街で、さまざまな草木をこまめに回り、受粉を助け、各地域の植物の命と農作物の豊かな実りを脈々とつないできました。
その土地特有の自然や人の暮らしに共存し、守ってきたのです。
「在来種であり、ポリネーター(花粉媒介者)である二ホンミツバチを保護し飼育することで、周辺の自然環境の維持に少しでも役立てたら」と布施さんは話します。
採蜜作業を終え、ハチに「ありがとう」と声を掛ける布施さん、温和な人柄が垣間見えました。