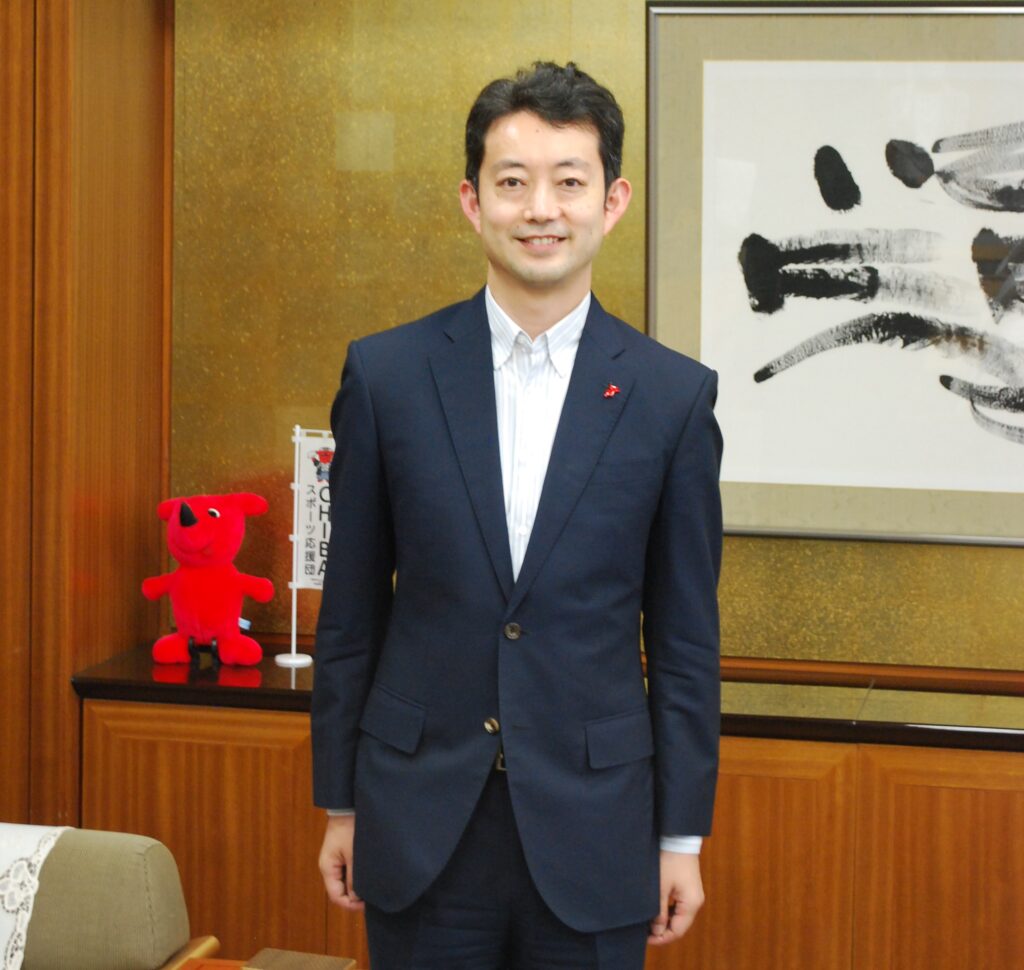千葉県の偉人・伊能忠敬を題材にし、忠敬ゆかりの地である香取市などで撮影が行われた映画『大河への道』が、5月20日(金)から全国で公開されます。
メガホンを取った中西健二監督に、見どころやキャスト、現場でのエピソードなどを聞きました。

こちらの記事もおすすめ
公開 2022/05/04(最終更新 2024/04/19)

立川志の輔の新作落語を映画化
――本作は、中井貴一さんの熱い思いがあって映画化に至ったそうですね。
はい、中井貴一さんが立川志の輔さんの落語「大河への道—伊能忠敬物語―」にひかれ、「ぜひ映画化したい」と企画したのが始まりです。
志の輔さんの原作と森下佳子さんの脚本を見させていただいたら、非常に面白かったんですね。「こんなに面白いものならどうしてもやりたい」と思い、すぐに引き受けました。
――どういった点を「面白い」と感じられたのでしょうか?
最初に現代の部分があって、時代劇に行くというところですね。そこからして面白いんですが、さらに登場人物が全員一人二役で、どちらの時代にも出てくる。どこかでイメージが重なり合うような役になっているのですが、現代劇と時代劇で全く同じ役柄というわけではなく、人によって近い役だったり遠い役だったりするんです。その面白味が増すようにするには、僕はあまり規則性に縛られない方がいいと思っていたので、なるべく役者さんのアイデアを柔軟に取り込んでいこうと考えていました。

見どころはキャストの、あうんの呼吸
――「アドリブなのかな?」と思うほど自然な、息の合ったやり取りが印象的でした。
実際アドリブで行っている部分はあります。今回は「喜劇」ということで、制限をかけずに役者さんにやりたいようにやってもらって、どんどん生かしました。「喜劇」って、他のジャンルと比べても役者さんが負うところがすごく大きいと僕は思っているんです。役者さんの力量で、見ている人が笑えるかどうかが決まってくる。なので、こちらは役者さんが出してくれるものをいかに損ねないで捉えるかということを考えていました。本当に素晴らしい役者さんがそろっていて、何も言わなくてもこちらが考えている以上のことを次々と出してくれるんですよね。特に、過去に共演して以来強い信頼関係がある中井さんと松山ケンイチさんコンビのシーンは、元々台本にあるものをどう膨らますかというところで二人のアイデアが盛り込まれて、すごく面白くなったと思っています。

――そういった現場のチームワークは、どのようにして作られたのでしょうか?
コロナ禍の撮影で、スケジュールがタイトになったり、条件が厳しくなったりということが多々ありました。それでも何とかいいものを作り上げようと、自然とチームワークが高まったと思います。
「時代劇を残したい」俳優・中井貴一の思い
――座長である中井貴一さんは、「時代劇を日本の文化、伝統として残したい」という思いがあり、この映画を企画したと聞きました。中井さんとは「時代劇」についてどんなお話をされましたか。
「時代劇としていい映画にしたい」という思いは、最初に話してくれました。僕も映画がものすごく好きで、古い映画もたくさん見てその素晴らしさを感じていますし、残していけたらと思っていましたので、「ぜひやらせていただきます」と。ただ僕は中井さんに比べれば時代劇に関しては経験が少し足りないので、現場でいろんなことを教えていただきました。

――現代劇と時代劇の割合が大体8対2である原作落語に対し、映画では3対7に逆転し、時代劇の分量が大幅に増えていますね。
僕自身は、現代劇と時代劇の比率は、映画としてすごく良いバランスだなぁと思って臨みました。もちろん落語は落語として面白いのですが、脚本では映画にするためのさまざまな工夫が重ねられています。なので、たびたび落語の方に戻ってしまうとかえって逆効果だと思いました。実は、原作の落語自体は最初に見て以降、あえて見ないようにしていたんです。この脚本を面白いと思ってもらうにはどうすればいいかを考えていたので、バランスが原作と変わったということは僕の中では意識しなかった。脚本の面白さを減らさないで、さらに面白い映画にするために僕がすべきこと、あるいはすべきでないことは何だろうというのを常に自問しながらやっていましたね。
伊能忠敬は「酸いも甘いもかみ分けた人」
――伊能忠敬の物語でありながら伊能忠敬本人が出てこないところも面白さの一つですが、これほどまでに弟子たちを突き動かし、今もなお地元の人たちから愛される伊能忠敬とは、どんな人物だったと思われますか?
最初は教科書で得られる知識しかなくて、「年を取ってから勉強し直して日本地図を作った偉い人」というくらいの認識でした。ところがこの映画を作るに当たって伊能忠敬について勉強してみると、佐原地域(現・千葉県香取市)の商人だった伊能家の婿養子になって家を立て直したとか、村で大飢饉が起こった時に自分の財産を使って村民を救ったとか、知らなかったことがたくさんあった。伊能忠敬を知るうちに、「この人は多分世の中のことを分かっている人だ」と思いました。酸いも甘いもかみ分けていないと、日本地図を作るという大事業を、単に学者的な考えだけでは成し遂げられなかったと思うんですね。どこか世の中や人間に対する把握の仕方が深かったから、いろいろな思いをしながらも乗り越えてやり続けられた人なんだろうなと。だからこそ、何とか意志を継いで地図を完成させようという人がいたのだろうし。改めて伊能忠敬という人の「深さ」を認識しました。

――地図を後世に残すことと映画を残すことは、どこか共通する部分があるのではないでしょうか?
日本地図ができていく過程を縁の下で支えていた人たちがいて、それで初めて成り立っているんだというストーリー建てに非常に共感しました。映画も表に立つ人がいて、その陰にたくさんのスタッフがいて初めて成立している代物なので、つながるところがあると。それも「ぜひこの映画をやりたい」と思った理由の一つです。
ロケ地・香取市の協力で受け取った思い
――クランクイン前に、香取市体育館で214枚の日本地図の複製パネルを広げてみたそうですね。
はい、その大きさにまず驚きました。体育館のかなりの部分を占めるほどだったので、これだけ大きいものをどう画面に収め、見る人に伝えるかを考えないといけないと思いましたね。香取市役所の商工観光課の方々と、地図を並べる作業も一緒にやらせていただいたんですが、実際やってみると、できているものを並べるだけでも大変だった。ということは、それを作り上げるということ、それも自分の足で歩いて、データを収集して一つ一つ線を引いて…というのは本当にすごいことだったんだなぁと、じわじわと来ましたね。途方もない労力の一端が感じられ、作中の地図の描き方に生かすことができました。

――千葉県内では、どこでロケを行ったのですか?
ロケ地は、伊能忠敬記念館、香取市役所、佐原の小野川沿いや「忠敬橋」、伊能忠敬の出生地である九十九里の海辺や千葉県庁などです。ただ、映っている部分だけでなく、裏側でも香取市には随分お世話になりました。京都での撮影が中心だったので、全て京都周辺で撮ってしまえば効率は良いんですが、非常に協力していただいて、香取市の皆さんの伊能忠敬に対する思いを感じた以上、「ここで撮らないと」という話になりました。クランクアップは伊能忠敬記念館の横で迎えたのですが、地元のお弁当屋さんにキャスト・スタッフ全員分のロケ弁を作っていただいて。とてもおいしいお弁当でした。4月10日に香取市で先行試写会を開催したのも、大変お世話になったからこそです。

――千葉県民としても、公開が楽しみです!
関わっているキャスト・スタッフ全員が一生懸命心を込めて作った作品です。私が思う「喜劇」とは、笑いながらも最後には人の感情がふに落ちる形で結実するもの。そんな映画になったと思うので、ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいと思います。

映画『大河への道』あらすじ

千葉県香取市役所の総務課に勤める池本保治(中井貴一)は、市の観光振興策を検討する会議で意見を求められ、苦し紛れに郷土の偉人・伊能忠敬の大河ドラマ制作を提案。思いがけずそれが通り、企画を進めるうちに、伊能忠敬は地図完成の3年前に亡くなっていたという驚きの事実が明らかに…。江戸と令和、2つの時代を舞台に明かされていく、日本初の全国地図誕生秘話。そこには地図を完成させるため、伊能忠敬の弟子たちが命を懸けて取り組んだ、とんでもない隠密作戦があった―。
予告編
キャスト
中井貴一 松山ケンイチ 北川景子 岸井ゆきの 和田正人 田中美央 溝口琢矢 立川志の輔 西村まさ彦 平田満 草刈正雄 橋爪功
原作:立川志の輔(河出文庫刊)/漫画:柴崎侑弘(小学館ビッグコミックス刊)
脚本/森下佳子(『JIN-仁』『ごちそうさん』『おんな城主 直虎』『義母と娘のブルース』)
音楽/安川午朗(『八日目の蝉』『殿、利息でござる!』『孤狼の血』)
監督:中西健二
主題歌/玉置浩二「星路(みち)」
製作幹事:木下グループ
製作プロダクション:デスティニー
配給/松竹
©2022「大河への道」フィルムパートナーズ
2022年5月20日(金)全国ロードショー
映画『大河への道』公式サイト https://movies.shochiku.co.jp/taiga/
こちらの記事もおすすめ