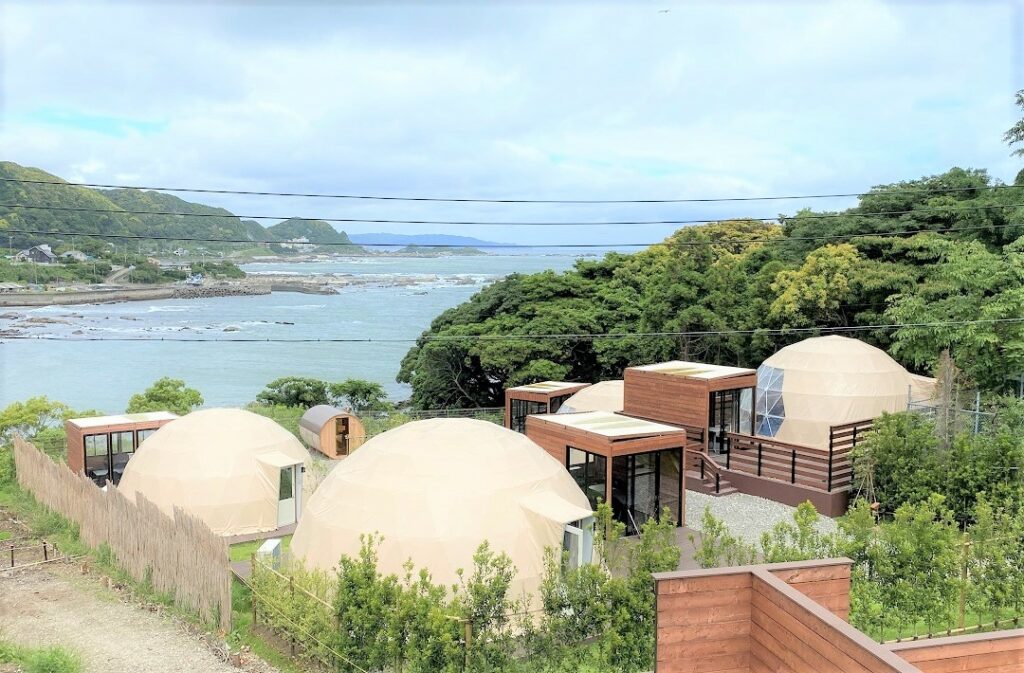印西市木下に、江戸時代後期から明治時代に利根川の河岸問屋(船問屋のこと)として栄えた吉岡家の資料や建造物などを展示する、吉岡まちかど博物館があります。
地域の歴史を学び、未来を考える場所です。
公開 2022/08/20(最終更新 2023/02/03)

ソバ
大手新聞社の記者を続け、定年延長も終わったので、地域の話題を取材したいと、地域新聞様にお世話になっています。明るく、楽しく、為になる話題を少しでも分りやすく紹介したいとネタ探しの日々です。子どもの頃から麺類が好きなのでペンネームにしました。
記事一覧へ明治時代の土蔵 貴重な絵や復元図

土蔵は2階建てで、敷地面積は約1千坪。
1891(明治24)年4月の建設で、吉岡家の活動を紹介する絵や写真がずらりと展示されています。
吉岡家は、香取神宮、鹿島神宮、息栖神社の三社や銚子を訪れる船を運航したり、水産物の中継基地にもなっていました。
土蔵にも展示されている「木下河岸三社詣出舟之図」には船の発着でにぎわう木下河岸の様子が見て取れます。
明治時代後期の木下河岸復元図には、吉岡家の蒸気船や、木下小学校・成田鉄道・旅館・酒屋・呉服屋・銀行などが描かれています。

庭には貝化石の灯籠水天宮の祠も
庭に出ると高さ2mほどの3本足の灯籠があります。
貝の化石で造られているのが特色です。
この化石は、木下貝層と呼ばるれ、約12万〜8万年前に古東京湾で堆積されたものです。
最初に木下地区で調査されたことから木下貝層と名付けられ、国の天然記念物に指定されています。
敷地内の小さな階段を上ると水天宮の祠があります。
水運の守護神で、安産の神としても霊験が知られています。
客を乗せて木下河岸を出た船が天候異変などで難破することがあったことから、1826(文政9)年に祭られたといいます。
しかし、明治時代の鉄道事業の発展の影響を受け、船問屋は衰退。
貴重な資料などは残されていたので、市民や大学生たちがボランティアで土蔵などを修復し、2004(平成16)年10月に吉岡まちかど博物館として開館しました。
ボランティアの男性は「地元の歴史を多くの人に知ってもらいたい。木下の町づくりの一環をを見てもらいたい」と話しています。
開館は毎月第1土曜、第3日曜の午後1時〜午後4時。入館無料。
問い合わせ/090-3529-4990 木下まち育て塾 伊藤
こちらの記事もおすすめ