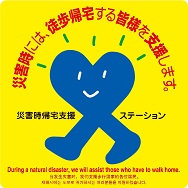予測不能な自然災害。むやみに恐れることなく、日常の延長線上に防災意識を取り入れる方法を、日本赤十字社千葉県支部で聞きました。
教えてくれたのは、ボランティア歴12年、防災セミナー講師をはじめ、地域防災に従事する千葉県赤十字防災ボランティアリーダー 橋本 奈緒美さんです。

公開 2022/08/24(最終更新 2024/01/04)

避難計画を立てておく

いざとなったときの避難判断は、内閣府の「避難情報に関するガイドライン」を目安にしてください。
警戒レベル3(高齢者等避難)、4(避難指示)から緊急度が増し、5(緊急安全確保)に至っては災害が始まっていると捉えて行動をすること。
特に高齢者や妊婦といった介助が必要な人は早い段階からの避難をお勧めします。
現在推奨されているのは、おのおのの状況で一番安全に避難できる場所に身を置く、「分散避難」です。
住宅が倒壊や損傷しているのであれば迷いなく指定避難所へ移動し、安全であれば自宅避難も選択肢の一つに入れてください。
介護や何らかのケアを受けている人向けの「福祉避難所(※)」も少しずつ増えてきています(※ケアが必要な人のみ。ケアマネージャーに相談を)。
大きな台風の予報などがあった時点で、警戒エリア外の友人や親戚宅を頼ることも一つの安全策です。
マンションの低層階で浸水の恐れなどがある場合、高層階の友人宅に身を寄せることも良いでしょう。
緊急時を想定して、普段から地域住人同士や友人とのコミュニケーションを取ることが大切です。
また、多くの指定避難所はペット同伴避難が可能です。集団生活となりますので、ケージに入れての同伴がマナー(ペットフードは持参)。
同じ動物といえど、盲導犬や聴導犬などの介助犬とペットは異なりますので、一緒の部屋に避難できるとは限りません。
他の避難者に迷惑が掛からないよう、普段から社会性の訓練をしておくことも大切です。
日頃から避難に備えた行動をあらかじめ決めておく防災行動計画書、「マイ・タイムライン(※2)」の作成もお勧めです。
まずは自分のエリアのハザードマップを各自治体で入手してください。
危険な箇所をチェックしながら避難経路を確認し、いざ台風予報などが出た際の行動をシュミレーションしながら落とし込んでいきましょう。
「携帯の充電をしておく」「水をためておく」など行動は具体的に書き込むこと、そして待ち合わせ場所も皆が分かりやすい所をピンポイントで決めておくこと。
話し合いをするたびに計画をアップデートしていきましょう。
※2 ちいき新聞版マイ・タイムライン(ダウンロードはこちらから!)
ローソンとファミリーマートのネットプリントでマイ・タイムラインを印刷できます。
番号:YKXM484TK4
期間:2022年09月21日 15時まで
※印刷代がかかります
持病がある、アレルギーがある人が気を付ける事
持病がある人は自宅避難でも薬の支援を受けられるようになっていますが、災害時用にどれくらいの薬をキープしておいた方がいいかなどは、日頃からかかりつけ医に相談しておきましょう。
また、各自治体の指定避難所には最新の情報が掲示されます。
避難所にドクターが来る日もお知らせされますので、救援物資を受け取りに行く際などに掲示板をチェックするようにしましょう。
避難所で配布されるものは皆が一様にして食べられるものですが、アレルギー対応食も一定数の用意がされています。
ただでさえ大変な避難生活、医療の提供もままならない中で命に関わることが起こってはいけません。
アレルギーがある人は積極的に申し出ましょう。
また、自分に合う非常食を数日分備蓄しておけば安心。
アレルギーは人それぞれ、自身である程度の判断をすることも必要です。
3~10日分の備蓄と、あると役立つアイテム
水は1日一人当たり2~3リットルは必要です。
その他にお茶やジュース類もあると好ましいですね。
非常用のトイレは大きめの段ボール箱2つとごみ袋、消臭剤の組み合わせで作ることができます。
使った後は口を閉めて、可燃ごみとして出せるまでベランダなどの屋外で保管しましょう。


その他、市販の歯磨きシートや携帯用マウスウォッシュは、歯ブラシがない時でもリフレッシュできるのでとても役に立ちます。

高齢者は避難時に入れ歯(洗浄剤)や老眼鏡、つえを忘れがちなので気を付けて。
女性において特筆すべきは、まずは生理用品。
自身に見合った量を、不安であれば2カ月分を目安にストックしましょう。
水分の吸収率が高いので、けがによる止血時にも使えます。
ドライシャンプーや体を拭くボディペーパーも重宝します。
何もない時は、ビニール袋にコップ一杯のお湯とハンドタオルを浸すだけで濡れおしぼりが完成します。
小さな子どものいる人は、おむつや液体ミルクを日常的に使いながら備蓄するとよいでしょう。
子どもの成長は早いので、シーズンごとにチェックをして頭から足先までのサイズ確認を忘れずに。
気付いたらサイズアウトしていた! なんてことを防げます。
眼鏡も就寝時などに身の回りに置いてほしい重要アイテムです。
新しい眼鏡を購入したら、古いものはスペア用として避難グッズの中へ入れておくと非常時に困ることがないでしょう。
非常食は食べながら備える
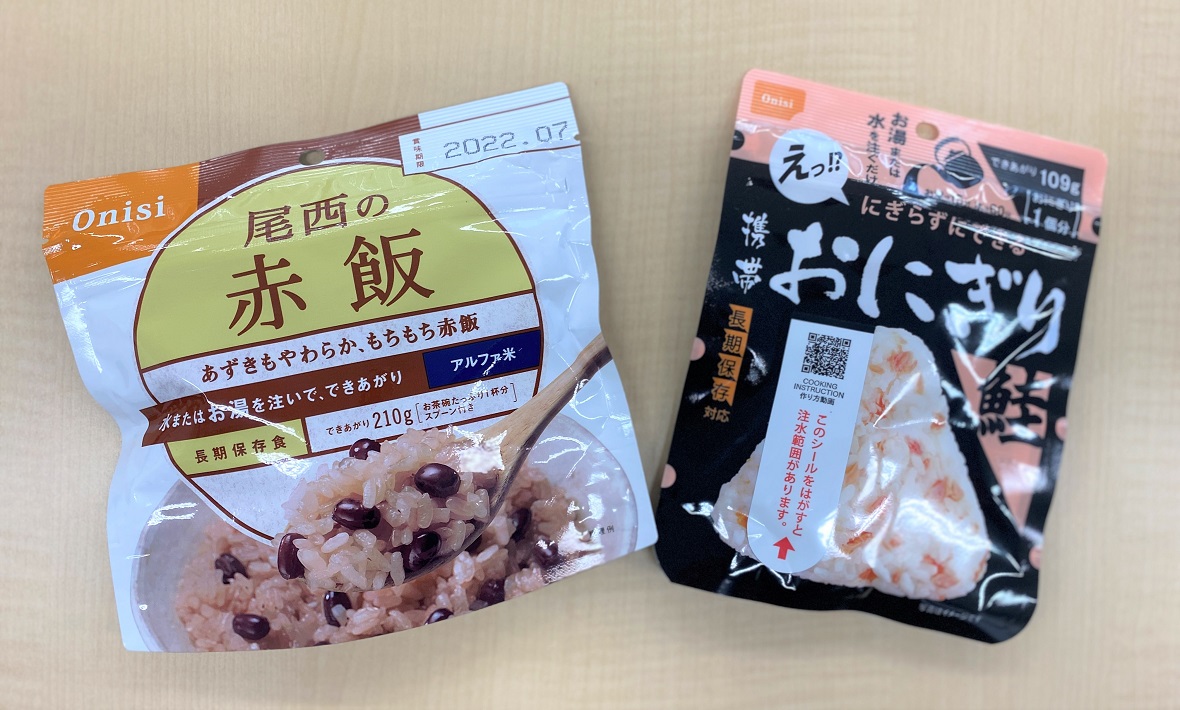
ロングライフの非常食はうっかり賞味期限が切れがちです。
食べ慣れている食品を多めに買って、食べた分を補充するという「ローリングストック」という方法をお勧めします。
手前に賞味期限が短いものを置いて入れ替えていけば無駄が省けます。
一定数を食べながら備蓄できて一石二鳥、ロングライフのものと併用すると効率的です。
例えばアルファ米のピラフ味やチキンライス味などは、オムレツを乗せたりカレーやビーフシチューをかけたりとゴージャスアレンジに。
赤飯や五目ごはんはおあげの中に入れておいなりさんにするなど、飽きずに楽しく賞味期限の管理と補充ができます。
定期的にパントリーに入れておき、日頃から確認する習慣を付けましょう。
たまに食卓に並べて、お子さんにも味に慣れさせておくといいでしょう。
避難生活のストレスを軽減してくれるお菓子などの嗜好品(しこうひん)のストックも忘れずに。
乾物や缶詰だけを使って食事を作る練習をする、「チャレンジデー」を設けてみるのも良いです。
被災時に食べるものとして、缶詰しかイメージが沸かないのは困ってしまいます。
一品でも工夫して上手に食べられるよう、肩肘を張らず普段やっていることの延長線上に少しだけ防災意識を置いて暮らしてみてください。
正しく情報収集をする
「まさか」の混乱の中では、情報が行動を左右します。
各指定避難場所が情報収集の場所としても大いに機能することをご存じでしょうか。
掲示板には、ボランティアセンター情報や待ち人などの伝言板、食料配給の時間など、最新の情報が掲示されますので、開設されたらこまめにチェックを。
日頃から自治体のメーリングサービスに登録しておくのもよいでしょう。
SNSは確かに便利ですが、出所の確かなものを情報として捉えること。
伝言ゲーム的な安易な拡散はやめてください。
また、国土交通省のサイト「防災情報提供センター」は、ハザードマップを始め、河川情報など現地を見に行かずとも正しい情報がキャッチできて便利です。
情報は自分で収集するという意識を忘れずに。