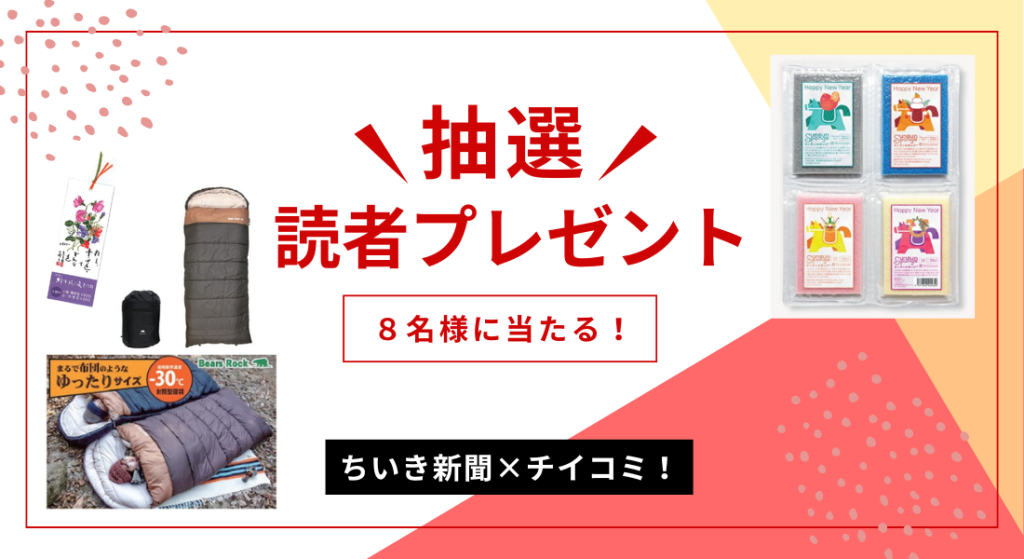つくば市と柏の葉キャンパスで知る「地域での学び」の役割
地域に根差した学びの場が今増えています。
意義や役割について現場の声を取材しました。
公開 2022/03/02(最終更新 2022/03/02)

編集部 モティ
編集/ライター。千葉市生まれ、千葉市在住。甘い物とパンと漫画が大好き。土偶を愛でてます。私生活では5歳違いの姉妹育児に奮闘中。★Twitter★ https://twitter.com/NHeRl8rwLT1PRLB
記事一覧へ目次
まちそのものを学びの場に 柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)

■アートコミュニケーションディレクター小山田裕彦さん
愛知万博の「ロボットプロジェクト」など各地でさまざまなプロジェクトを手掛ける自称「やらかし隊長」。柏の葉キャンパスでは「えびせんさん」の愛称で親しまれています。
子どもが自ら学ぶよう仕掛ける
千葉県柏市で、公(行政)・民(市民や企業)・学(大学や専門機関)共同のまちづくりを推進するUDCK。小山田さんは同センターで、地域を巻き込んだ多くの催しを企画してきました。
その一つが、まちそのものを学びの場としてとらえるプロジェクト「五感の学校(現・未来こどもがっこう)」。アーティストや大学教授らを講師に招き、店舗の壁や窓ガラスに落書きをしたり、散策しながらまちの匂いを集めたりとユニークなワークショップを定期的に開催しています。
「子どもが自ら『学びたい、知りたい』という気持ちを持つことが大切」と小山田さん。同じテーマでも、子どもによって興味を持つポイントはさまざま。教えるのではなく、あくまで「気付き」を与える場として取り組んでいるそうです。

▲お店の窓ガラスに子どもたちが自由に落書きするワークショップも
地域の大人と子どもの交流が自然発生することもワークショップの醍醐味。「子どもに関わることで大人自身も柔軟になる。大人が変わればまちの雰囲気も変わる。伸び伸びとした雰囲気の中で子どもたちが成長できます」とほほ笑みます。
「子どもの発想は想像を超える」と話す一方で、調整する力も育みたいと小山田さん。例えば、職業体験の場を提供する「ピノキオプロジェクト」では、企画や交渉なども子どもたちが大人と一緒に担当。「段取りを経験することで、実現までのプロセスを具体的にイメージする訓練になります」と続けます。
寛容性のあるまちが子どもたちを育てる
まちは子どもに刺激を与えるヒントであふれているというのが小山田さんの持論。「今は通学路に仕掛けを作れないかと模索中。電信柱にランダムに数字を書く。すると子どもたちは勝手に意味を付けて遊びに使うと思うんです。欄干を見るとつい乗りたくなる子どもの好奇心も危険がない形で伸ばせないかな…」とアイデアは無限です。
そして、もう一つ大切にしているのが寛容性。もし子どもたちが数人で道端に座っていたら注意するのではなく、小山田さんは理由を尋ねます。すると「ここからの景色がきれいだから」など思ってもみなかった返事が来ることも。それがヒントになり、新たな企画につながるケースも少なくありません。
「頭ごなしに否定するのではなく、『本当にだめなのか』『どうしたらOKなのか』をわれわれ大人も立ち止まって考えてみることです」と話すように、理由や動機を掘り下げることが、気持ちよく暮らせる環境づくりの近道なのかもしれません。
子どもの考える力を育み、大人も一緒に学ぶ。そうすることで、自発的に活動の輪が広がり地域がより良くなる。その循環を促す手段の一つが「学びの場」なのだと教えてくれました。
柏の葉アーバンデザインセンター
問い合わせ 04(7140)9686
HP https://www.udck.jp/
科学の楽しさを広める 茨城県科学技術振興財団

■つくばサイエンスツアー推進課 課長 中村充さん
昨年から同財団に携わり、市内研究機関と連携したツアーやイベントを企画・運用。サイエンスツアーのガイドをするために日々猛勉強中!
気軽に科学に触れるバスツアーを実施
学園都市として知られ、さまざまな研究機関が集まる茨城県つくば市。
科学技術の普及啓発を目指す(一財)茨城県科学技術振興財団では、市内およそ150の研究機関のうち、約50の施設と連携し、各施設の見学や紹介を一般向けにコーディネートしています。
中でも好評なのが土日祝に運行する「つくばサイエンスツアーバス」。「地図と測量の科学館(国土地理院)」や「筑波宇宙センター(JAXA)」といった代表的なスポット6カ所を循環するバスで、1日大人500円と手軽に利用できます。
「研究の成果を発表する場として開放しているといっても、一般の人が研究所を訪れるには少しハードルが高い。ツアーにすることで誰でも気軽に簡単に見学できます」と話すのは、ツアーを手掛ける中村充さん。
第1・3土曜日は、中村さんらスタッフが同行し、ガイドも行います。「展示を見ただけでは理解できないことを分かかりやすくお伝えしています。

▲スタッフガイド同行コースの様子
例えば、『地図と測量の科学館』には、屋外に地球と月の模型が展示してありますが、実は大きさ、距離ともに1200万分の1の縮尺になっています。パッと見ただけではわかりませんが、そんな解説を聞くと宇宙の壮大さを体感できますよね」とにっこり。他にも、身の回りにあるものを例に挙げて、科学技術が私たちの生活を支えていることを実感してもらえるよう働き掛けています。
貴重な研究施設を身近なものに
数キロメートルの間隔で多様な研究機関が林立するつくば市は、まさに「科学のまち」。各機関の取り組みや研究成果に子どもたちが触れ、驚きや感動を持つことで、学ぶ意欲が刺激されれば、未来の研究者の育成にもつながります。
しかし、各研究機関の第一の役割は調査や研究の発表の場であり、その成果を正確に、分かりやすく伝えることはとても難しい課題だといいます。「そこを私たちがサポートをして施設と多くの人をつなげ、人々の新たな興味や関心のきっかけづくりに貢献したいと考えています」と中村さん。
地域の財産ともいえる研究施設をより身近なものにし、一人でも科学に興味を持つ子どもが増えることで、多くの人の暮らしが豊かになる—。ツアーバスは、そんな壮大な夢の第一歩となるのかもしれません。
※「スタッフガイド同行コース」は要予約。新型コロナウイルスの影響により、ツアー中止、またはバスが運休することがあります。事前にHPを要確認。
つくばサイエンスツアーオフィス (一財)茨城県科学技術振興財団
問い合わせ 029(863)6868
HP https://www.i-step.org/tour/index.html