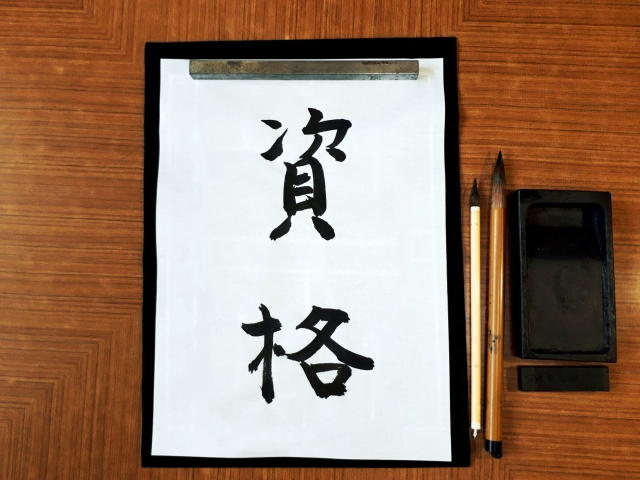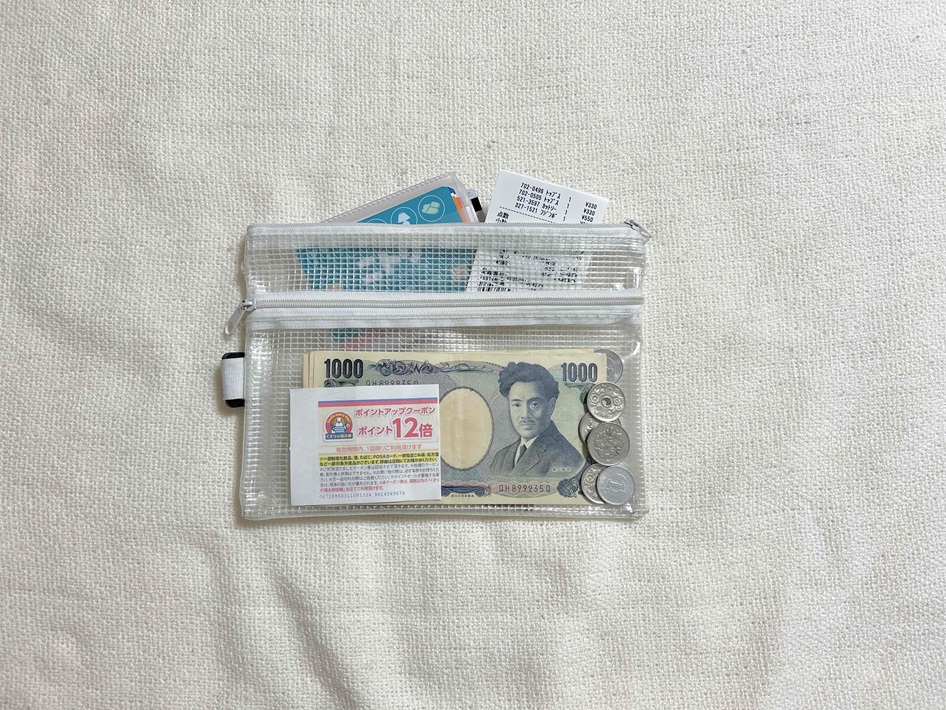収入アップやスキルアップなど、将来的なキャリアのために資格を取りたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
資格の取得はキャリアの選択肢を広げられるだけではなく、専門的な知識とスキルを身に付けたという自信にも繋がります。社会人の場合は、スクールを上手に利用すると無理なく資格取得を目指せるでしょう。
この記事では、社会人に特におすすめしたい資格12選とスクール選びのポイントをご紹介します。
近くのスクールをさがす
公開 2023/12/30(最終更新 2024/07/17)

目次
社会人が資格を取るメリットとは?
社会人が資格を取るメリットは、次の4つです。
・専門知識やスキルがあることを証明できる
・今いる職場での評価や収入アップを目指せる
・職業選択の幅が広がる
・自分に自信が持てるようになる
資格を取得すると、専門的な知識やスキルが身に付いていることを証明できます。業種や職種によっては資格の有無で顧客の信頼度が変わってくるため、業務内容に合わせた専門資格を取得しておくと有利に働けるでしょう。また、資格は取得するまでに地道な労力が必要です。その努力の過程が認められれば、今いる職場での評価や収入アップに繋がるかもしれません。
また、職業選択の幅がグッと広がるのも、資格を取得するメリットです。転職を考えている場合など、希望する業種や職種に合わせた資格を持っておくと、未経験でも採用される可能性が高まります。将来的に独立を考えているなら、業務独占資格の取得を目指すのもおすすめです。
社会人にとって、仕事と資格試験の勉強を両立させるのは容易なことではありません。しかし、少しずつ努力を重ねていく中で、「自分にもできる」といった自信に繋がるはずです。自分に自信が持てれば、今後のキャリアを前向きに考えられるようにもなるでしょう。
キャリアアップに!仕事系の人気資格
キャリアアップを目指す方におすすめしたい仕事系の人気資格を7つご紹介します。
・宅地建物取引士(宅建士)
・マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)
・日商簿記
・TOEIC
・ファイナンシャルプランナー(FP)
・産業カウンセラー/シニア産業カウンセラー
・日本語教師
どれも業界を問わず幅広く役立てられる資格なので、取得しておいて損はありません。外国人と一緒に仕事をするのも珍しくない今、国際的な資格も取っておきたいところです。
宅地建物取引士(宅建士)
| 試験名 | 宅地建物取引士資格試験(宅建試験) |
|---|---|
| 受験料(税込) | 8,200円 |
| 難易度 | 比較的取得しやすい |
| 合格率 | 13.1~17.9%(過去5年分より算出) |
| 学習期間の目安 | 3~6カ月 |
| 試験日程 | 例年10月の第3日曜日 |
| 受験資格 | 日本国内在住であれば誰でも受験可能 |
宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引に関する専門知識があることを証明する資格です。不動産を売買する際、顧客が不利益を被らないために取引内容について重要な情報を説明しなければなりません。この重要事項の説明は、宅建士の有資格者のみが行える独占業務です。
宅建士資格試験は毎年20万人以上もの受験者数を誇り、知名度も高い国家資格といえるでしょう。合格率は過去5年で13.1~17.9%と決して簡単とはいえませんが、国家資格全体で見るなら比較的取得しやすいとされています。不動産だけではなく建築や金融など様々な業界で活かせる資格なので、キャリアの幅を広げたい方におすすめです。
学習期間の目安は、ある程度知識のある方なら3カ月、初学者の場合は6カ月ほど見ておくと良いでしょう。試験は年に1回、例年10月の第3日曜日に実施されています。
マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)
| バージョン | 一般レベル | 上級レベル |
|---|---|---|
| 受験料(税込) | 10,780円 | 12,980円 |
| 難易度 | 比較的取得しやすい | 比較的取得しやすい |
| 合格率 | 80% | 60% |
| 学習期間の目安 | 1~3カ月 | 2~4カ月 |
| 試験日程 | 全国一斉:月1~2回、日曜日 随時:試験会場による | 全国一斉:月1~2回、日曜日 随時:試験会場による |
| 受験資格 | 誰でも受験可能 | 誰でも受験可能 |
マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)は、WordやExcelなどマイクロソフト社が開発したアプリケーションの利用スキルが身に付いていることを証明する資格です。多くの企業でパソコンを使った業務が主流となっている今、WordやExcelなどのスキルはすべての社会人にとって必須といえるでしょう。
とはいえ、パソコンに不慣れな方も多いのが現実です。そんな中で、WordやExcel、PowerPointを使ってスムーズに資料作成や表計算ができると、社内での自分の評価アップにも繋がります。業種や職種を問わず活かせるという意味でも、汎用性の高い資格として人気です。
試験には、一般レベルと上級レベルの2種類あります。どちらも、公式には難易度や合格率は公開されていません。業務で日常的にオフィスソフトを使っている方であれば、比較的勉強も資格取得もしやすいでしょう。他の資格に比べると学習期間が短いことから、パソコンが苦手な方でも十分に合格を狙えます。
試験の実施については、毎月1~2回、日曜日に全国一斉で行うものと、最寄りの試験会場が設定した日時で行うものの2種類です。申し込み方法が異なるだけで、受験料や試験内容、合格認定証の内容に差はありません。
日商簿記
| 級数 | 3級 | 2級 | 1級 |
|---|---|---|---|
| 受験料(税込) | 2,850円 | 4,720円 | 7,850円 |
| 難易度 | 比較的取得しやすい | 難しい | 非常に難しい |
| 合格率(過去5回分より算出) | 30.2~50.9% | 17.5~26.9% | 9.8~12.5% |
| 学習期間の目安 | 1~5カ月 | 3~8カ月 | 6~12カ月 |
| 試験日程 | 例年2月、6月、11月 | 例年2月、6月、11月 | 例年6月、11月 |
| 受験資格 | 誰でも受験可能 | 誰でも受験可能 | 誰でも受験可能 |
日商簿記は、経理関連の専門知識があることを証明できる資格です。企業を円滑に運営していくためには、適切なお金の管理が欠かせません。日商簿記では基本的な帳簿の付け方に始まり、財務諸表の見方なども学べます。すべての企業にとって、経理はなくてはならない存在です。日商簿記の資格を取得しておくと、様々な業界の経理部門で活躍できるでしょう。
なお、日商簿記の資格試験は3級、2級、1級の順に難易度が上がります。キャリアアップや転職をより有利に進めたいなら、最低でも2級以上は必要です。将来的に公認会計士や税理士などを目指しているなら、1級の取得も視野に入れると良いでしょう。
級数別の難易度を見ると、3級は比較的取得しやすいとされています。2級以上になるとグッと難易度が上がり、高レベルの計算力が必要です。単にテキスト内容を暗記するだけでは、合格は難しいでしょう。目安学習期間は3級が1~5カ月、2級は3~8カ月です。1級については、6~12カ月と長いスパンでの学習計画を立てる必要があります。
なお、3級と2級の試験日程は年に3回、例年2月、6月、11月の実施です。1級は年2回、6月と11月に実施されています。3級と2級はネット試験にも対応しており、試験会場が設定した日時で随時受験可能です。
TOEIC
| 受験料(税込) | 7,810円 |
| 難易度 | 難しい |
| 平均スコア | 601.8~625.6点(過去5回分より算出) |
| 学習期間の目安 | 100点上げるのに3~5カ月 |
| 試験日程 | 毎月1~2回 |
| 受験資格 | 誰でも受験可能 |
TOEIC(TOEIC Listening & Reading Test)は、英語によるコミュニケーションスキルの有無を証明する全世界共通の英語能力試験です。国際化が進む今、日本人にとっても英語は欠かせないスキルとなりつつあります。海外とのやりとりが多い企業への転職を考えている方は、ぜひチャレンジしてみてください。
TOEICの中で最もよく知られているのは、10~990点までのスコアを示すリスニング&リーディングのテストです。合否判定はない代わりに、点数の高さがそのまま英語力の高さとして判断されます。資格として活かしたい場合は、最低でも700点以上は目指しましょう。TOEICは受験資格や受験回数に制限がないので、自分の英語力を試したい方にもおすすめです。
試験の難易度については、一概にいえません。ただ、英語はほとんどの日本人にとって母国語ではないため、難しいと感じる方が多い傾向にあります。英語に苦手意識を持っている方がTOEICの勉強を始めるとなると、そのハードルはさらに上がるでしょう。
学習期間は、スコアをどれだけ伸ばしたいかで変わってきます。100点上げるのに3~5カ月の勉強が必要とされていますが、期間にとらわれず日々コツコツと学習を続けることが語学習得への近道です。試験は月1~2回ペースで頻繁に開催されているので、ぜひ積極的にチャレンジしてみてください。
ファイナンシャルプランナー(FP)
| 級数 | 3級 | 2級 | 1級 |
|---|---|---|---|
| 受験料(非課税) | 学科のみ:4,000円 実技のみ:4,000円 学科+実技:8,000円 | 学科のみ:5,700円 実技のみ:6,000円 学科+実技:11,700円 | 【FP協会実施分】 学科:- 実技:20,000円 【きんざい実施分】 学科:8,900円 実技:28,000円 |
| 難易度 | 比較的取得しやすい | 難しい | 非常に難しい |
| 合格率(過去5回分より算出) | 【FP協会実施分】 学科:74.78~88.25% 実技:77.67~90.33% 【きんざい実施分】 学科:37.19~56.00% 実技:49.46~59.80% | 【FP協会実施分】 学科:42.16~56.12% 実技:52.02~62.11% 【きんざい実施分】 学科:15.75~29.07% 実技:32.80~40.80% | 【FP協会実施分】 学科:- 実技:93.00~99.00% 【きんざい実施分】 学科:3.51~13.00% 実技:80.10~86.07% |
| 学習期間の目安 | 1~3カ月 | 3~5カ月 | 6~10カ月 |
| 試験日程 | 2024年より毎月随時 | 例年1月、5月、9月 | 【FP協会実施分】 学科:- 実技:例年9月 【きんざい実施分】 学科:例年1月、5月、9月 実技:例年2月、6月、9月 |
| 受験資格 | 誰でも受験可能 | ・AFP認定研修修了者 ・3級FP技能検定合格者 ・2年以上のFP業務実務経験 | ・CFP認定者 ・1級FP技能検定合格者、など |
ファイナンシャルプランナー(FP)は、相談者のライフイベントや目標に合わせた人生設計をお金の面からサポートする資格です。取得しておくと、保険や金融、住宅、不動産など、様々な業界での活躍が期待できるでしょう。お金に関する専門知識は、自分の生活を守るのにも役立ちます。経済面での苦労を避けたい方にもおすすめの資格です。
ファイナンシャルプランナーの資格を取得するには、国家資格のFP技能士、もしくは民間資格のAFPや CFPを目指す方法があります。AFPやCFPの取得には、最低でもFP技能士2級以上が必要です。まずFP技能士3級からスタートし、レベルを上げていく中でAFPやCFPの取得を目指すのが良いでしょう。
試験を実施しているのは、日本FP協会と金融財政事情研究会(きんざい)の2団体です。合格率は異なりますが、学科試験の内容についてはどちらも変わりません。レベル別に難易度を見ると、3級は比較的取得しやすいといわれている一方で、2級でグッと難易度が上がります。1級については、学科試験を突破すること自体が至難の業です。学科試験をいかに攻略するかが勝負といえるでしょう。
学習期間は3級が1~3カ月、2級は3~5カ月、1級は6~10カ月ほどが目安です。試験日は、3級については2024年から毎月ネット受験ができるようになります。2級の学科・実技と1級の学科は例年1月、5月、9月の実施、1級の実技は2月、6月、9月の実施が一般的です。
産業カウンセラー/シニア産業カウンセラー
| 試験名 | 産業カウンセラー試験 | シニア産業カウンセラー試験 |
|---|---|---|
| 受験料(税込) | 学科:11,000円 実技:22,000円 | 面接:- |
| 難易度 | 難しい | 難しい |
| 合格率 | 学科:65.0% 実技:61.1% | – |
| 学習期間の目安 | 6~10カ月 | 1~2年 |
| 試験日程 | 学科:例年1月、6月 実技:例年1月、7月 | 例年2月 |
| 受験資格 | ・協会が行う所定の講座を修了した者 ・大学院研究科で心理学、心理学隣接諸科学、人間科学、人間関係学のいずれかの名称を冠する専攻(課程)の修了者 ・4年制大学学部卒業者で協会が指定する所定の単位を取得した者 | ・産業カウンセラーの資格登録者かつ協会が指定するシニア産業カウンセラーの養成講座を修了した者 ・産業カウンセラーの資格登録者かつ大学院研究科で心理学、心理学隣接諸科学、人間科学、人間関係学のいずれかの名称を冠する専攻の修了者かつ協会が指定するシニア養成講座を修了した者 |
産業カウンセラーは、メンタルヘルス対策やキャリア形成、人間関係構築の3つを軸に働く人びとをサポートする資格です。シニア産業カウンセラーは、産業カウンセラーの3本柱をさらに掘り下げた知識をもとにコンサルティングを行います。
産業カウンセラーの合格率は、学科・実技ともに6割程度です。数字だけ見れば、あまり難しくないように思えるかもしれません。しかし、高等教育機関で専門的に学んできた方でも4割は不合格になっているので、簡単に取得できる資格ではないことがわかります。
シニア産業カウンセラーの合格率は、2019年までの4年間で学科が約4.5~7割、実技が約2~6割でした。産業カウンセラーの資格を取得してから一定の条件を満たさないとシニア産業カウンセラーの受験資格を得られないため、こちらも難易度が高い試験であることがわかります。なお、シニア産業カウンセラーは2019年から面接のみの実施となっているため、今後の合格率や難易度に影響があるかもしれません。
どちらの資格も、日本産業カウンセラー協会が定める養成講座を修了する必要があります。学習期間の目安は産業カウンセラーが6~10カ月、シニア産業カウンセラーが1~2年です。試験日は、産業カウンセラーの学科が例年1月と6月、実技が1月と7月に開催されています。シニア産業カウンセラーの面接は、例年2月に行われているようです。
近年は働き方の多様化が進む一方で、職場に馴染めないなどの悩みを抱える方も増えてきました。そんな方に寄り添い、問題を自分で解決できるように導くのが産業カウンセラー/シニア産業カウンセラーの使命です。メンタルヘルス対策やキャリア形成、人間関係構築をサポートできる人材は、どこの職場でも求められています。資格を持っておくと、幅広い業界で活躍できるでしょう。
おすすめ
日本語教師
| 試験名 | 日本語教育能力検定試験 |
|---|---|
| 受験料(税込) | 17,000円 |
| 難易度 | 難しい |
| 合格率(過去5年分より算出) | 28.2%~30.8% |
| 学習期間の目安 | 6~12カ月 |
| 試験日程 | 例年10月 |
| 受験資格 | 日本国内在住であれば誰でも受験可能 |
日本語教師として正しい日本語を教える知識と能力が備わっていることを証明するためには、以下の3つのどれかを満たしている必要があります。
・日本語教員養成課程のある4年制大学で規定の日本語教育専攻・副専攻課程を修了
・公益財団法人日本国際教育支援協会が主催する日本語教育能力検定試験に合格
・民間スクールの日本語教師養成講座で420時間のカリキュラムを修了
3つのうち、日本語教育能力検定試験に合格すると日本語教師の資格を取得できます。日本語のネイティブである日本人なら簡単に取得できるように思いがちですが、合格率は約3割と高めの難易度。その理由は、出題範囲が幅広いためです。日本語や日本語教育に関する内容はもちろんのこと、様々な知識を網羅的に身に付けなければなりません。
学習期間の目安としては、6~12カ月の長期スパンで設定するのがおすすめです。試験は年に1回で、例年10月に開催されています。
海外からの留学生や労働者の中には、日本語能力が十分とはいえない方も少なくありません。日本での生活にいち早く慣れてもらうためにも、正しく日本語を教えられる人材が強く求められています。日本語教師としての知識やスキルを持っておくと、国内外で日本語学校を開く際にも役立つでしょう。
自分磨きに!趣味系の人気資格
自分を磨きたい方にピッタリな趣味系の人気資格を5つご紹介します。
・着付け技能士
・乗馬ライセンス
・アロマテラピー検定
・カラーコーディネーター検定
・整理収納アドバイザー
何事も、無理をすると長続きしません。しかし、趣味として楽しみながらであれば、資格取得へのモチベーションも上がるのではないでしょうか。趣味系の資格の中には、極めると仕事として収入に繋げられるものもあります。人生をより豊かにするためにも、ぜひチャレンジしてみてください。
着付け技能士

着付け技能士は、着物や浴衣などの着付けができることを証明する資格です。普段着として和服を着る機会は減ったものの、大切な日には和装でキメたいという方も多いのではないでしょうか。また、外国人旅行者の間で着物や浴衣は非常に人気が高いため、着付けができる人材が求められています。
そこで持っておくと有利なのが、着付け技能士の資格です。全日本着付け技能センターが主催する国家検定で、2級と1級とがあります。着物の歴史に始まり、男女の着物の違いや帯の種類など、着物に関するあらゆる知識を学習可能です。着付けを学ぶと、古来より日本人が大切にしてきた所作やマナーも身に付けられます。改めて日本文化と向き合いたい方には、特におすすめです。
乗馬ライセンス

乗馬ライセンスは、乗馬技術がどのレベルにあるかをチェックするための認定制度です。5級からスタートし、4級、3級へとレベルアップしていきます。3級まで取得すると、馬場2級、障害3級、エンデュランス3級などへの挑戦も可能です。馬との基本的な接し方に始まり、常歩や軽速歩、駈歩など乗馬の技術を身に付けられます。
日本では乗馬人口がまだまだ少なく、乗馬ライセンスを持っておくとコミュニケーションのきっかけとして役立つかもしれません。また、馬場や障害、エンデュランスなどのライセンスまで取得できれば、競技大会への出場も目指せます。馬が好きな方は、取得を目指してみてはいかがでしょうか。
アロマテラピー検定

アロマテラピー検定は、香りを安全に生活の中に取り入れるための知識があることを証明する資格です。精油の使用方法、効果や効能など、アロマ全般について学べます。香りには人をリラックスさせる効果があるといわれており、ストレス解消や心と身体のバランスを整えたいときなどにもおすすめです。
近年は、医療や介護などの現場で香りを使った癒し効果に注目するところも増えてきました。生活に香りを取り入れることで、より人生が豊かに彩られるでしょう。香りに興味のある方は、ぜひ取得を目指してみてください。
カラーコーディネーター検定

カラーコーディネーター検定は、色の違いや性質を理解した上でコーディネートに活かせる資格です。「色」は、ファッションやメイク、食事など、私たちの生活の中に必ず存在しています。一つひとつの色の特徴を知って効果的に組み合わせれば、その人に一番似合うスタイルの提案や彩り豊かな食卓の演出に繋げられるでしょう。
また、色の使い方はビジネスの現場でも非常に重要です。同じ商品やデザインでも、色彩一つで売上が大きく変わる場合もあります。商品開発や広告作成など、色を実践的に役立てられるのもカラーコーディネーター検定のメリットです。おしゃれが好きな方はもちろんのこと、色の知識を身に付けて仕事の幅を広げたい方は、受験してみてはいかがでしょうか。
整理収納アドバイザー

整理収納アドバイザーは、散らかりにくく片付けやすい環境作りをアドバイスする資格です。「なかなか物を捨てられない」「片付けてもすぐ散らかってしまう」「整理整頓が苦手」といった原因を探り、どうすれば解決できるのかを理論的に身につけられます。
家庭以外に職場でも活かせるのが、整理収納アドバイザー資格の大きな強みです。物が整理されてすっきりとした職場は印象アップに繋がるだけではなく、働く人びとの精神的なゆとりも生まれるでしょう。きれいな職場で雰囲気良く仕事をしたい方は、整理収納アドバイザーの資格取得を目指してみてください。
学習スタイルで比較!社会人でも通いやすい資格スクール選びのポイント
働いている社会人にとって、仕事と資格試験の勉強との両立はハードルが高いと感じるかもしれません。社会人が資格取得を目指すなら、資格スクールの利用がおすすめです。ここでは、通いやすい資格スクール選びのポイントを解説します。
通学講座のメリット・デメリット
通学講座のメリットとデメリットは、以下の通りです。
メリット
・講師から直接講義を受けられる
・その場で講師に質問などができる
・勉強する習慣を付けられる
・同じ志を持つ仲間ができる
デメリット
・高額な費用がかかりがち
・スケジュール調整が難しい
・通える人や範囲が限定される
通学講座は、なんといっても講師から直接講義を受けられるのが大きなメリットです。その場で質問もできるので、より理解が深まりやすいでしょう。知識をしっかり自分の中に定着させられれば、合格や資格取得の可能性がグッと近付きます。
また、通学講座は決まった曜日や時間帯に受講するスタイルが一般的で、自然と勉強する習慣をつけられるのもうれしいポイント。同じ志を持つ仲間との出会いがあるのも、通学講座ならではの魅力です。
一方で、他の学習手段に比べると通学講座は費用が高くなりがちです。また、学習スケジュールがある程度決められているため、勤務時間帯や休日が不規則だと仕事との両立が難しいかもしれません。学校が遠方にしかないなど、通える人や範囲が限定されてしまうのも通学講座のデメリットです。
通信講座のメリット・デメリット
通信講座のメリット・デメリットについて、以下を参考にチェックしておきましょう。
メリット
・カリキュラムや教材の質が高い
・映像教材が充実している
・質問や添削などのサポートが手厚い
・自分のペースで進められる
デメリット
・完全独学よりは費用がかかる
・質問や添削の返信にタイムラグがある
・モチベーションの維持が難しい
どのスクールを選ぶかにもよりますが、通信講座はカリキュラムや教材の質が高いところが多いです。講座によっては映像教材も充実しており、実際に教室にいるかのようなリアルな講義を受けられるでしょう。学習を続けやすいように、質問や添削などのサポート体制も整っています。また、自分のペースで無理なく勉強を進められるため、仕事と両立しやすいのも通信講座のメリットです。
反面、通信講座にもやはり教材費などの費用がかかるので、完全独学よりは割高になります。質問や添削が返ってくるまでにタイムラグが生じるのも念頭に入れておいてください。また、通信講座は基本的に1人で学習を進めるため、モチベーションの維持が難しいといったデメリットもあります。
「今日は勉強したから明日は休む」「毎日最低2時間は勉強する」といったように、ルールを決めてメリハリを付けると勉強を習慣化しやすいでしょう。通信講座のサポート体制も上手に活用すれば、合格率や資格取得率も上げられるはずです。
オンライン講座のメリット・デメリット
最後に、オンライン講座のメリットとデメリットをご紹介します。
メリット
・自宅からいつでも受講できる
・コミュニケーションが苦手でも参加しやすい
・リラックスした環境で受講できる
・感染リスクを抑えられる
デメリット
・通信環境に左右されやすい
・集中力が途切れがち
・実践型の講座には不向き
オンライン講座は録画されている講義を視聴するスタイルが多いため、生活リズムに合わせて自宅からいつでも受講できます。勤務形態が変則的な方でも、勉強と仕事を両立させやすいでしょう。また、人とのコミュニケーションが苦手な方の中には、オンライン講座なら参加のハードルが下がるという方もいるかもしれません。自分が慣れ親しんだ環境の中でリラックスして受講できるのも大きな魅力です。新型コロナウイルス感染症などの感染リスクを抑えたい方にも向いています。
一方で、オンライン講座はインターネットの通信環境に左右されやすく、映像が突然切れる、音声が遅れて届くなどのトラブルが起こりがちです。自分好みの環境下で受講できる分、様々な誘惑に負けて集中力も途切れやすいでしょう。また、オンライン講座は講師がそばで直接指導できるわけではないので、手や身体を実際に動かしながらスキルを身につけるには向いていません。
オンライン講座の場合、テキストや資料の閲覧などもウェブで完結できることが多い傾向にあります。紙媒体で購入する必要がない分、通信講座などよりも受講費用を安く抑えられるでしょう。ただし、パソコンやネット回線など、オンライン受講の環境が整っていなければ、まずそこから揃えなければなりません。状況次第では、通学講座や通信講座よりも高額なコストがかかる可能性があることは覚えておいてください。
まとめ
社会人におすすめの資格12選とスクール選びのポイントを解説しました。資格を取ると専門知識やスキルがあることを証明できるので、今いる職場での評価や収入アップも可能です。転職や独立を考えている方は、業界や職種の選択肢も増やせるでしょう。資格取得は地道な労力が必要ですが、努力した分だけ必ず自分の力となり、自信にも繋がります。より充実した人生を送るために、資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。