食から千葉市を盛り上げるべく、縄文グルメ推進委員会が発足しました。
カギとなるのは、イボキサゴ(じょうもん貝)という小さな巻貝です。
公開 2022/02/05(最終更新 2022/02/02)

編集部 モティ
編集/ライター。千葉市生まれ、千葉市在住。甘い物とパンと漫画が大好き。土偶を愛でてます。私生活では5歳違いの姉妹育児に奮闘中。★Twitter★ https://twitter.com/NHeRl8rwLT1PRLB
記事一覧へ世界最古の調味料で市の名物グルメを
市内に多くの貝塚が点在し、縄文時代から多くの人に愛されてきた千葉市。
そんな千葉市を「縄文のまち」にしたいと、2021年12月に縄文グルメ推進委員会が本格始動しました。
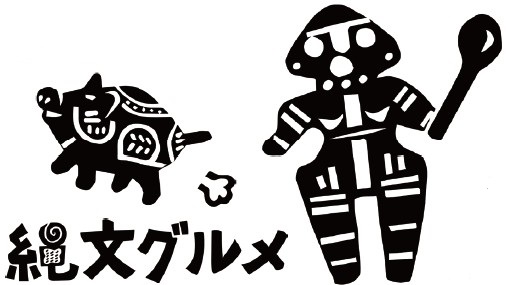
委員会代表の小川智之さんは、「『千葉市』と聞いて、誰もが共通で思い浮かべるイメージが正直なところ、今はありません。そこで地域を想起させる名物を作りたいと考えたのがきっかけです」と発足の理由を話します。
多くの人が興味を持つのはやはり「食」。
おいしい食べ物に語りたくなるストーリーが合わさることで、食文化にとどまらない広がりを見せるのでは、と考えました。
着目したのは、千葉市が掲げる「都市アイデンティティ戦略プラン」の一つにある加曽利貝塚。
加曽利貝塚から出土する貝殻の大半を占めるのは、あさりなどの二枚貝ではなく「イボキサゴ」という巻貝。
直径2センチほどの小さな貝で、縄文人はだしを取るのに使っていたと推測されています。
戦後の東京湾の埋め立てで、一時は姿を消したが、10年ほど前から木更津市の盤洲干潟で大量発生し、養殖ノリに被害を及ぼしていました。
縄文人にとってはごちそうですが、今は厄介者になってしまったイボキサゴ。
「『世界最古の調味料』ともいえるこのだしを活用し、『縄文グルメ』として市内で普及させることで、新たな名物が誕生するだけでなく、漁師さんたちの助けにもなります」と小川さんは熱を込めます。
4月より本格始動 縄文グルメが続々
本来は大量の貝を殻ごと煮てだしを取る必要がありましたが、淑徳大学の研究チームと地元企業の連携により、無加調だしの加工に成功。
手間なく気軽に使えるようになりました。
和食はもちろん、イタリアンやフレンチとも相性抜群だといいます。
昨年末から一部の加盟店でプレスタートし、今年の4月に正式スタート予定。

加盟店の店頭には、ロゴが入ったのぼりが立ちます。
さらに、より市民に親しみを感じてほしいと、イボキサゴを「じょうもん貝」の愛称で呼ぶことにしました。
「じょうもん貝はタウリンがしじみの20倍以上も含まれる栄養価が高い食品。二日酔いにもいいので、お酒の席のシメでじょうもん貝のだしを飲む『〆だし』文化も発信したいですね」と小川さん。
今後の展開が楽しみです。

問い合わせ
メール/info@jomon-g.org
縄文グルメ推進委員会

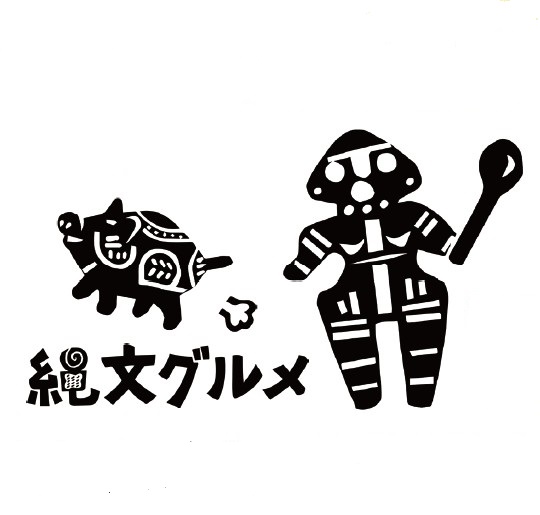









0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)









