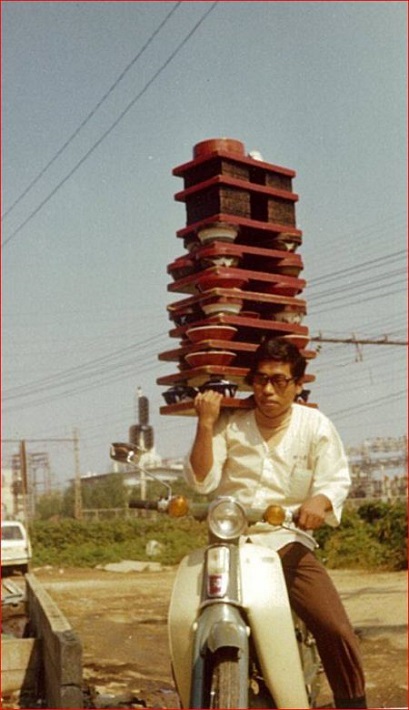琴といえば、正月に流れる宮城道雄の名曲「春の海」でなじみが深いですが、その琴の製造元が三郷市にあります。
1964(昭和39)年創業のみつや琴製造株式会社を訪ね、伝統の和楽器「琴」の製作工程を取材しました。

公開 2021/09/07(最終更新 2021/09/06)

箏と琴の違いは?
「こと」には正確には「箏」と「琴」があります。
箏は、柱と呼ぶ可動式の支柱で弦の音程を調節。
琴には柱がなく、弦を押さえる指の位置で調節します。
洋楽器に例えるなら、フレットのあるギターと、指の押さえの位置で音を決めるバイオリンのような違いがあります。
同社は13弦、17弦、20弦、25弦の「箏」と海外モデルを製作していますが、本文中は社名にそろえ「琴」で表記します。
琴の製作工程
琴の製作は原木の製材・乾燥から始まります。
原木には、木目が詰まり音の響きが優れている寒冷地の桐、特に会津桐が重用されています。

皮を削って形を整えた原木を2年以上乾燥させ、木目を生かして琴の原型を削り出し、「甲」を作ります。
この作業で琴の骨格と音の響きが決まるといいます。

甲作りの次は「巻き」。
甲に精緻な装飾を加え、琴として仕上げます。


甲作りから完成までは1、2カ月を要します。
同社には甲作りと巻き、それぞれに専門の職人がおり、総勢18人の職人が作業に携わります。
「甲作りには原木全体を俯瞰的に見るセンスと大胆さが、巻きには繊細さと根気が求められます」と、代表取締役の光安慶太さん。
17弦、20弦、25弦のモデルでは、国内生産の90%以上を同社が占めています。
邦楽の普及拡大にも精力的に貢献
近年の邦楽人口の減少に加えコロナ禍も影響して、琴をはじめ伝統和楽器を取り巻く環境は厳しく、後継者不在で廃業する例も少なくありません。
同社もオイルショックやリーマンショックなどの危機はありましたが、当初は関東のみだった販売エリアを全国に拡大して乗り越えてきました。
最近では海外モデルの製作を下支えに、熟練から中堅まで多くの職人を擁することで、伝統技術を継承。
琴の修理も受け付けており、他社製品も対応しています。
光安さんは(一社)全国邦楽器組合連合会の理事長も務めます。
萩生田光一文部科学大臣との面談や、文化庁「邦楽普及拡大推進事業」に協力し、邦楽と和楽器製作の継続と普及に尽力しています。(取材・執筆/松島徹八)